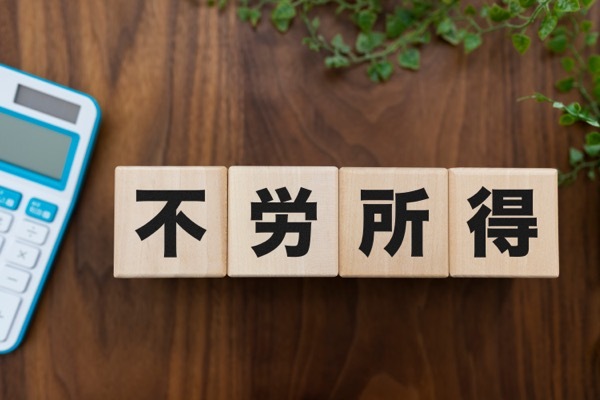
「働かなくても収入が得られたら……」誰しも一度は夢見る不労所得。しかし、具体的にどんな種類があり、どう始めれば良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不労所得の基礎知識から具体的な種類、メリット・デメリット、そして初心者が失敗しないための注意点まで、分かりやすく解説します。
1.不労所得の基礎知識

まず、不労所得とは何か、そして私たちが普段得ている労働所得とどう違うのかを理解しましょう。この基本的な知識が、不労所得を築くうえでの第一歩となります。
1-1.不労所得とは?
「不労所得」とは、一般的に、日々の労働や時間的拘束を伴わずに得られる収入を指します。例えば、株式の配当金や不動産の家賃収入のように資産運用によって得られるものから、ブログやYouTubeなどの広告収入のように、一度仕組みを作れば継続的に収益が発生するものまで、幅広い手段が含まれます。
初期段階ではある程度の手間や時間が必要ですが、その後は継続的な管理が少なく、比較的安定した収入が得られる可能性がある点が共通しています。
1-2.不労所得と労働所得の違い
不労所得とは異なり、会社に雇用されて働くことで得られる収入は「給与所得」と呼ばれます。国税庁によれば、給与所得には、会社員や役員が受け取る給料、賞与、賃金などが含まれます。これらは、雇用契約や職務上の立場に基づいて支払われるもので、自らの労働や時間を継続的に提供することによって得られる収入です。
このように給与所得は、資産の保有や運用によって得られる不労所得とは、性質が大きく異なります。
2.おすすめの不労所得10選
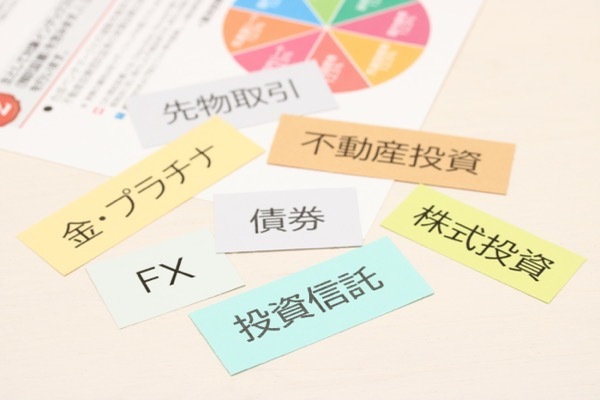
一口に不労所得といっても種類はさまざまで、それぞれ必要な知識やリスクの大きさが異なります。中には初期費用が高額だったり、運用に手間がかかったりするものもありますが、正しく取り組めば将来的に収入につながる可能性があります。
ここでは、比較的取り組みやすく、不労所得として活用されやすい10種類を厳選し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく紹介します。
2-1.株式投資(配当金・株主優待)
株式投資は、企業が発行する株式を購入し、その企業のオーナーの一人となることです。不労所得としては、企業が得た利益の一部を株主に還元する「配当金」があります。
企業の成長に伴う株価上昇(キャピタルゲイン)も期待できますが、ここでは主に定期的な収入源としての側面に焦点を当てます。証券口座を開設すれば比較的誰でも始めやすく、NISAなどの非課税制度を活用することで節税効果も期待できます。
ただし、株価は常に変動しており、企業の業績や経済状況によっては配当金が減額されたり、支払われなくなったりするリスクも伴います。銘柄選定には企業分析などの知識も必要となるため、情報収集と学習が重要です。
2-1-1.メリット
- 比較的少額から投資を始めることができる
- 企業の業績が良ければ、増配による配当金増加が期待できる
- 株主優待制度がある企業では、金銭以外のメリットも受けられる
- NISAなどの非課税制度を利用すれば、税制面で有利になる
- 経済や企業経営に関する知識が身につく
2-1-2.デメリット
- 株価の変動により、投資元本を割り込むリスクがある
- 企業の業績悪化や倒産により、配当金が減少または無配になる可能性がある
- 株主優待は廃止・変更されることがある
- 銘柄選定には専門的な知識や情報収集が必要
- 長期的な視点と継続的な管理が求められる
2-2.不動産投資(家賃収入)
不動産投資は、マンションやアパート、戸建てなどの不動産を購入し、それを他人に貸し出すことで家賃収入を得る方法です。インフレに強く、資産価値が残りやすい特徴があります。金融機関からの融資を利用してレバレッジを効かせることができるため、少ない自己資金で大きな投資を始めることも可能です。
一方、空室リスクや家賃滞納リスク、物件の老朽化による修繕費の発生、自然災害リスクなど、さまざまなリスクが伴います。また、物件管理の手間や、固定資産税などの税金も考慮に入れる必要があります。物件選定、入居者対応など、専門的な知識やノウハウも求められるため、信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵となります。
2-2-1.メリット
- 安定した家賃収入が期待でき、インフレに強い資産となる
- 金融機関からの融資を利用することで、レバレッジ効果が期待できる
- 多くの場合、生命保険の代わりになる団体信用生命保険に加入できる
- 減価償却費などを経費計上することで、節税効果が期待できる
- 物件によっては売却益(キャピタルゲイン)も狙える
2-2-2.デメリット
- 空室リスクや家賃滞納リスク、自然災害リスク、金利上昇リスクなどがある
- 物件の修繕費や管理費、固定資産税などの維持コストがかかる
- 流動性が低く、すぐに現金化することが難しい
- 物件選定や管理には専門的な知識が必要で、手間もかかる
関連記事:不動産投資とは?仕組みやメリット・デメリット、理想の利回り、始め方を解説
2-3.投資信託(分配金)
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散投資し、その運用成果を投資額に応じて分配する金融商品です。不労所得としては、定期的に支払われる「分配金」があります。少額から購入でき、専門家が運用を行うため、投資初心者でも始めやすいのが特徴です。また、一つの投資信託で複数の銘柄に分散投資されるため、リスク分散効果も期待できます。
ただし、運用成績によっては分配金が支払われない、あるいは基準価額が下落して損失を被る可能性もあります。また、購入時手数料や信託報酬(運用管理費用)などのコストもかかるため、商品選びは慎重に行う必要があります。
2-3-1.メリット
- 少額から購入でき、分散投資を手軽に行える
- 運用の専門家に任せられるため、初心者でも始めやすい
- 株式、債券、不動産など多様な投資対象があり、選択肢が豊富
- 積立投資を利用すれば、時間分散によるリスク軽減効果も期待できる
- NISAの対象商品も多く、非課税メリットを受けられる
2-3-2.デメリット
- 元本保証ではなく、運用成績によっては損失を被るリスクがある
- 購入時手数料や信託報酬などのコストがかかる
- 分配金が支払われない、あるいは減額される可能性がある
- 多くの商品があるため、自分に合ったものを選ぶのが難しい
- 運用成果は投資先ファンドマネージャーの実力に左右される
2-4.FX(スワップポイントなど)
FX(外国為替証拠金取引)は、異なる国の通貨を売買して利益を得る取引です。不労所得の観点では、日々の取引による差益よりも、「スワップポイント」を目的とした長期保有が注目されます。
スワップポイントとは、通貨ペアにおける金利差をもとに発生する金利調整額であり、高金利通貨を買い、低金利通貨を売るポジションを保有し続けることで、一定の条件下では日々スワップポイントを受け取れる可能性があります。スワップポイントは毎営業日に反映されるため、“保有しているだけで受け取れる収入”と捉えることもできます。
ただし、スワップポイントの金額は市場の金利情勢によって日々変動します。条件によっては受け取るのではなく、支払う側になることもあり、不労所得として安定的に得られるとは限りません。加えて、FX全体に共通する価格変動リスクがあるため、スワップポイント狙いであっても一定のリスク管理と知識が求められます。
2-4-1.メリット
- ポジションを保有しているだけで、スワップポイントを日々受け取れる可能性がある
- 定期的に売買をしなくても収入が発生するため、手間が少ない運用が可能
- 金利差が継続する限り、ある程度の収益見通しを立てやすい
- 他の投資と並行して取り組みやすい(運用の分散が可能)
2-4-2.デメリット
- スワップポイントの額は各国の金利動向により日々変動し、将来の受取額が不安定になる可能性がある
- 金利差が逆転した場合、スワップポイントを支払う側になることもある
- 保有中に為替レートが大きく変動すると、スワップ収入を上回る損失が生じるリスクがある
- 高金利通貨は政治・経済の不安定な国の通貨であることが多く、急な政策変更などにより金利環境が悪化するリスクもある
2-5.債券投資(利子)
債券投資は、国や地方公共団体、企業などが資金調達のために発行する「債券」を購入し、定期的に利子を受け取り、満期日(償還日)には額面金額(元本)が払い戻される仕組みです。利回りは低い傾向にありますが、安定した収益を求める投資家にとっては魅力的な選択肢といえます。
ただし、発行体の信用リスク(倒産などにより利子や元本が支払われないリスク)や、金利変動リスク(市場金利が上昇すると債券価格が下落するリスク)も存在します。また、市場で売却できる債券の場合、途中で売却する際は時価での取引となるため、金利変動や需給状況によっては元本を下回る可能性もあります。市場で自由に売買できない債券や、中途換金に制限がある商品もあるため、購入前に条件をよく確認することが重要です。
2-5-1.メリット
- 定期的に安定した利子収入が期待できる
- 満期まで保有すれば、原則として額面金額が償還される
- 価格変動リスクが比較的小さく、安全性が高いとされる商品が多い
- 発行体が国や優良企業であれば、信用リスクも低い
- 個人向け国債など、少額から購入できる商品もある
2-5-2.デメリット
- 株式投資に比べて、期待できるリターン(利回り)は低い傾向にある
- 発行体の財政状況悪化や倒産によるデフォルト(債務不履行)リスクがある
- 金利上昇局面では、債券価格が下落する金利変動リスクがある
- 途中で売却する場合、市場価格によっては元本割れする可能性がある
- インフレに弱い側面がある(物価上昇率が利回りを上回る場合、実質的な価値が目減りする)
関連記事:個人向け社債の利回りランキング!選び方のポイントも解説
2-6.ブログ・アフィリエイト
ブログ・アフィリエイトは、自身で運営するブログやWebサイトに広告を掲載し、その広告経由で商品やサービスが購入されたり、広告がクリックされたりすることで報酬を得る仕組みです。初期費用を抑えて始められ、自分の好きなことや得意なことをテーマにできる自由度の高さが魅力です。一度人気記事や収益を生む仕組みができれば、継続的な収入が期待できます。
しかし、成果が出るまでには時間がかかり、SEO対策やライティングスキル、マーケティング知識など、多岐にわたるスキルが求められます。また、Googleのアルゴリズム変動や広告主の都合によって収入が大きく変動するリスクもあります。継続的なコンテンツ作成とWebサイト改善の努力が欠かせません。
2-6-1.メリット
- 比較的少ない初期費用で始めることができる
- 自分の好きなことや得意なことをテーマにしやすい
- 場所や時間に縛られずに作業ができる
- 一度収益化の仕組みが作れれば、継続的な収入が期待できる
- ライティングスキルやWebマーケティングの知識が身につく
2-6-2.デメリット
- 収益化までに時間がかかり、成果が出ない可能性もある
- SEO対策やコンテンツ作成など、専門的な知識と継続的な努力が必要
- Googleのアルゴリズム変動や広告主の規約変更など外的要因で収入が不安定になることがある
- 競合が多く、差別化が難しい場合がある
- 常に新しい情報を収集し、Webサイトを更新し続ける必要がある
2-7.動画配信(YouTubeなど)
動画を制作してYouTubeなどの動画配信プラットフォームで公開し、広告収入やチャンネルメンバーシップ、スーパーチャット(投げ銭)などで収益を得る方法です。スマートフォン一つあれば始められ、趣味や特技を活かしたコンテンツで人気を集めれば、大きな収入を得ることも可能です。ファンとの交流も魅力の一つです。
しかし、質の高い動画を継続的に制作するには、企画力、撮影・編集スキル、そして時間と労力が必要です。また、視聴者数や再生回数を増やすためには、トレンドの把握やマーケティング戦略も重要になります。競合も多く、収益化のハードル(チャンネル登録者数や総再生時間など)をクリアするのも容易ではありません。
2-7-1.メリット
- スマートフォン一つで比較的低コストで始められる
- 自分の趣味や特技、専門知識を活かしたコンテンツを発信できる
- 広告収入以外にも、メンバーシップや投げ銭など多様な収益化手段がある
- 人気が出れば、大きな収益や影響力を得られる可能性がある
- ファンとのコミュニケーションを楽しめる
2-7-2.デメリット
- 質の高い動画を継続的に制作・編集するには多大な時間と労力、スキルが必要
- 収益化の基準(チャンネル登録者数、総再生時間など)を達成するのが難しい
- 競合が多く、視聴者の注目を集めるためには工夫が必要
- プラットフォームの規約変更やアルゴリズム変動の影響を受ける
- 誹謗中傷やプライバシー侵害などのリスクも考える必要がある
2-8.印税・著作権収入
印税・著作権収入とは、書籍、音楽、写真、イラスト、ソフトウェアなどの著作物を制作し、その利用許諾や販売に応じて得られるものです。一度ヒット作を生み出せば、長期間にわたって安定した収入を得られる可能性があります。自分の創造性や専門性を活かせる点が大きな魅力です。
ただし、作品が評価され、収益に結びつくまでには時間と才能、そして運も必要です。特に未経験から始める場合は、作品を世に出すまでのハードルが高く、出版社やプラットフォームに採用されるための競争も激しいです。また、著作権の管理や契約に関する知識も求められます。時代の変化と共に需要がなくなるリスクも考える必要があります。
2-8-1.メリット
- 一度ヒット作が生まれれば、長期間にわたり継続的な収入が期待できる
- 自分の創造性や才能、専門知識を形にして収入につなげられる
- 作品が利用される限り、自分が直接働かなくても収入が発生する
- 社会的な評価や達成感を得られることがある
- デジタルコンテンツの場合、在庫リスクがない
2-8-2.デメリット
- 作品が収益を生むまでに時間と労力がかかり、必ずしも成功するとは限らない
- 才能やスキル、そして運も必要とされる
- 市場のニーズやトレンドの変化により、収入が不安定になる可能性がある
- 著作権の管理や契約に関する知識が必要
- 模倣や著作権侵害のリスクがある
2-9.駐車場・駐輪場経営
駐車場・駐輪場経営は、所有している土地や借りた土地を活用して、時間貸しや月極でスペースを提供し、その利用料を得る方法です。比較的管理の手間が少なく、特別な専門知識もあまり必要としないため、初心者でも始めやすい不労所得の一つとされています。立地条件が収益を大きく左右し、駅近くや商業施設の周辺など、需要の高い場所であれば安定した収入が期待できます。
すでに土地を保有している場合は初期費用を抑えやすい一方、新たに土地を購入する場合には取得費用や整備費用が必要です。また、競合の出現や周辺環境の変化による需要の低下、不正利用やトラブル対応の手間といったリスクも考慮する必要があります。
2-9-1.メリット
- 比較的管理の手間が少なく、専門知識もあまり必要としない
- 土地さえあれば、少ない初期投資で始められる場合がある
- 立地が良ければ、安定した収益が期待できる
- 他の土地活用方法に比べて、転用が比較的容易
- 運営を管理会社に委託することも可能
2-9-2.デメリット
- 土地の取得費用や整備費用など、初期投資が高額になる場合がある
- 立地条件に収益が大きく左右される
- 競合の出現や周辺環境の変化による収益減少リスクがある
- 税金(固定資産税、都市計画税など)の負担がある
- 不正利用や利用者間のトラブル、放置車両などの問題が発生する可能性がある
2-10.コインランドリー経営
コインランドリー経営は、洗濯機や乾燥機を設置した店舗を運営し、利用客からの利用料金で収益を得るビジネスモデルです。共働き世帯においては家事の時短ニーズが、また一般家庭においては布団などの大型洗濯物の洗濯ニーズが存在し、これらはコインランドリー利用の動機となり得ます。基本的には無人経営が可能で、日常的な管理業務(清掃、集金、洗剤補充など)を委託することもできます。
ただし、店舗の準備費用(内外装工事費など)や設備購入費など、初期投資が高額になる傾向があります。また、競合店の出現や、水道光熱費の高騰による収益圧迫、機械の故障やメンテナンス費用なども考える必要があります。立地選定が非常に重要で、地域住民のニーズを的確に捉える必要があります。
2-10-1.メリット
- 比較的安定した需要が見込め、景気に左右されにくい
- 基本的には無人経営が可能で、管理業務を委託することもできる
- 現金収入が主であるため、キャッシュフローが良い
- 節税効果が期待できる場合がある(減価償却など)
2-10-2.デメリット
- 店舗の準備費用(内外装工事費など)初期投資が高額になる
- 水道光熱費の変動が収益に影響を与える
- 機械の故障やメンテナンスに費用と手間がかかる
- 競合店の出現による影響を受けやすい
- 立地選定が非常に重要で、失敗すると収益化が難しい
3.不労所得のメリット

不労所得は生活の安定に役立つだけでなく、将来への備えやライフスタイルの柔軟性にもつながります。ここでは、不労所得がもたらす4つの代表的なメリットを紹介します。
3-1.経済的なゆとりが生まれ、将来の選択肢が広がる
不労所得があれば、生活費の一部を労働以外の収入でまかなえるようになります。これにより、収入面での不安が軽減され、働き方や暮らし方の自由度が高まります。例えば、毎月一定の配当金や家賃収入があることで、収入源が一つに偏らず、転職や独立、早期リタイアといった将来の選択肢も現実的になります。
3-2.時間に追われない、柔軟なライフスタイルが実現しやすくなる
不労所得は、継続的に収入が入ってくる仕組みを構築することで、働き続けなくても一定の収入を得られる可能性があります。その結果、フルタイムで働く必要がなくなったり、労働時間を短縮したりできれば、家族との時間や趣味、学び直しなど、自分の意思で時間の使い方を決めやすくなります。
3-3.心にゆとりが生まれ、安心感につながる
収入源が一つだけでは、体調不良や職場の変化などで不安を感じることもあります。不労所得があることで、収入の柱が増え、万が一のときにも一定の収入が確保できるという安心感が生まれます。経済的な不安を軽くできることは、精神的な安定にもつながる大きなメリットです。
3-4.収入源を分散して経済的リスクに備えられる
不労所得を持つことは、収入源を分散することにもなります。給与収入だけに頼る状態から、複数の収入ルートを持つことで、経済的な変化や突発的な出来事に対する抵抗力が高まります。特に景気変動や雇用環境の変化に備える意味でも、リスクを分散する方法として不労所得を取り入れることは有効な選択肢といえるでしょう。
4.不労所得のデメリットと注意点

夢のある不労所得ですが、良い面ばかりではありません。始める前に知っておくべきデメリットや注意点があります。失敗を避けるためには、これらを理解しておくことが重要です。
4-1.「不労」ではない初期段階の努力と時間
多くの不労所得は、実際には収入を得る仕組みをつくる段階で、自らの時間と労力をかける必要があります。例えば不動産所得を得るには、物件の選定や購入手続き、ローンの契約、入居者の募集・管理、清掃、税務処理など、さまざまな作業が必要です。これらの準備段階はれっきとした「労働」であり、こうした作業を丁寧に積み重ねなければ、安定した収入を得ることは難しいでしょう。
4-2.収入の不確実性と変動リスク
不労所得といっても、実際にはある程度の初期費用や専門知識が求められるものが多くあります。例えば株式投資では、銘柄の選定や市場動向の把握が不可欠です。また、収入の仕組みやリスクについて正しく理解していないと、思わぬ損失につながる可能性があります。確かな知識と計画性が、不労所得を安定的に得るための前提となります。
4-3.必要な資金や専門知識の壁
不労所得を得る方法の中には、まとまった初期投資や専門的な知識が求められるものがあります。例えば、不動産投資を始める際には、多くの場合、高額な資金が必要となります。株式投資は少額から始めることも可能ですが、生活の支えになるような安定した配当収入を目指す場合や、特定の銘柄に集中的に投資する際には、ある程度の資金が必要になることも理解しておくべきでしょう。
4-4.情報の見極めと詐欺被害への警戒
「短期間で高収益」「誰でも簡単に稼げる」といった甘い言葉には注意が必要です。不労所得への関心が高まるなかで、詐欺的な投資案件や副業ビジネスも増えており、SNSや動画広告を通じて広まるケースが多く見られます。中には、実在する有名人を装って信頼させようとする手口もあります。安易に個人情報や資金を提供する前に、その情報が本当に信頼できるかどうかを冷静に見極めることが重要です。
4-5.税金と確定申告の義務
不労所得がある場合でも、税金の申告義務からは逃れられません。例えば、給与以外の収入が一定額を超えると、会社員でも確定申告が必要になります。不動産収入や株式の配当、事業収入などは、それぞれ異なる申告方法や経費計上のルールがあります。こうした税務上の手続きに対応するためには、事前に正しい知識を身につけておくことが重要です。知らずに放置してしまうと、後から追徴課税などの問題に発展する可能性があります。
関連記事:サラリーマンでも確定申告が必要な人は?得をするケースや申請方法
5.不労所得を得る手順

不労所得を得るためには、計画的なステップを踏むことが大切です。ここでは、不労所得を得るための基本的な5つのステップを紹介します。
5-1.目標設定
まず、「なぜ不労所得を得たいのか」「月にいくらくらいの不労所得を目指すのか」「いつまでにそれを達成したいのか」といった具体的な目標を設定しましょう。目標が明確であればあるほど、取るべき行動や選択すべき不労所得の種類が見えてきます。
例えば、「老後の生活資金の足しに月5万円」という目標と、「早期リタイアのために月30万円」という目標では、戦略や必要な努力の度合いが大きく異なります。具体的で測定可能な目標を立てることが、モチベーションを保つことにもつながります。
5-2.情報収集と学習
目標が決まったら、さまざまな不労所得の種類について情報収集を行い、それぞれのメリット・デメリット、リスク、必要な知識やスキルを学びましょう。書籍やWebサイト、セミナー、経験者の話など、情報源は多岐にわたります。
一つの情報源をうのみにせず、複数の情報源から客観的な事実を集めることが重要です。自分が興味を持った分野については、深く掘り下げて学習し、基本的な仕組みや専門用語を理解しておくことで、失敗のリスクを減らすことができます。
5-3.自分に合う方法を選ぶ
収集した情報と自身の目標、資金力、スキル、リスク許容度、興味関心などを総合的に踏まえて、自分に最も適した不労所得の手段を見つけましょう。
例えば、資金が少ないうちはブログや少額の株式投資から始め、資金が増えてきたら不動産投資に挑戦するなど、段階的にステップアップすることも有効です。背伸びをしすぎず、無理なく継続できる方法を選ぶことが成功への近道です。他人にとって良い方法が、必ずしも自分にとって良い方法とは限りません。
5-4.少額から実践
どの不労所得を選ぶにしても、最初から大きな資金を投じたり、大規模に始めたりするのは避け、まずは少額から、あるいは小規模で実践してみましょう。
実際にやってみることで、本やネットの情報だけでは分からなかった課題や、自分なりのコツが見えてきます。小さな成功体験を積み重ねることが自信につながり、失敗したとしても損失を最小限に抑えることができます。試行錯誤を繰り返しながら、徐々に規模を拡大していくのが賢明な進め方です。
5-5.継続と改善・拡大
不労所得の構築は、一朝一夕に達成できるものではありません。一度始めたら、すぐに結果が出なくても諦めずに継続することが重要です。そして、定期的に成果を振り返り、問題点があれば改善策を考え、実行していくプロセスが欠かせません。
市場環境の変化に対応したり、新しい知識を学んだりしながら、より効率的に、より多くの不労所得を得られるように仕組みを改善・拡大していくことを目指しましょう。地道な努力の積み重ねが、大きな成果へとつながります。
6.不労所得で失敗しないコツ

不労所得を目指す多くの人が、残念ながら途中で挫折したり、思わぬ損失を被ったりすることがあります。ここでは、不労所得で失敗しないために押さえておきたい4つのコツを紹介します。
6-1.「楽して儲かる」という幻想を捨てる
不労所得と聞くと、「楽して簡単に儲かる」というイメージを持つかもしれませんが、それは大きな誤解です。どんな不労所得であれ、安定した収入を得るまでには、相応の知識習得、準備、努力、そして時間が必要です。
初期段階ではむしろ多大な労力がかかることも少なくありません。「楽して儲かる」という甘い考えは捨て、地道な努力を継続する覚悟を持ちましょう。この心構えが、詐欺的な話にだまされないための第一歩にもなります。
6-2.常に学び、情報をアップデートする
不労所得を取り巻く環境は、経済状況、法律、税制、テクノロジーの進化などによって常に変化しています。過去に有効だった方法が、現在も通用するとは限りません。そのため、常に新しい情報を収集し、学び続ける姿勢が欠かせません。
書籍を読んだり、セミナーに参加したり、専門家の意見を聞いたりして、知識やスキルをアップデートし続けましょう。現状に満足せず、変化に対応していく柔軟性が、長期的に不労所得を維持・拡大するための鍵となります。
6-3.分散投資・リスク分散を意識する
一つの不労所得にすべての資金や労力を集中させるのは、非常にリスクが高い行為です。その収入源が何らかの理由で途絶えた場合、大きな打撃を受けてしまいます。複数の異なる種類の不労所得を組み合わせたり、同じ種類の不労所得でも投資先を分散させたりすることで、リスクを軽減することができます。
例えば、株式投資なら複数の銘柄に、不動産投資なら複数の物件に分散するといった具合です。リスク許容度に合わせて、バランスの取れたポートフォリオを構築しましょう。
6-4.長期的な視点を持つ
不労所得の魅力は「安定して得られる収入」にありますが、それを維持・成長させるには、時間をかけて取り組む姿勢が欠かせません。投資環境や法律、税制は数年単位で変化するため、目先の利益だけにとらわれると、変化に対応できなくなるリスクがあります。
例えば、税制や金利、経済状況の変化によって収益性が左右されることもあるため、短期的な利益に一喜一憂せず、継続的な見直しと改善を重ねながら、自分に合った形を時間をかけて築いていくことが求められます。
7.不労所得は、選び方と向き合い方が重要

不労所得は、働かずに得られる収入とされていますが、その実現には準備や判断力が求められます。仕組みをつくる段階では、時間や手間がかかることも少なくありません。また、どの方法にも一定のリスクがあり、確実な成功が約束されているわけではない点にも注意が必要です。
重要なのは、自分の目的や状況に合った方法を選び、正しい知識をもとに取り組むことです。焦らず、長期的な視点で続けることが、将来的な収入の柱となる可能性を高めてくれます。まずは情報を集め、自分にとって現実的な選択肢から始めてみましょう。不労所得は、正しく向き合えば、家計や暮らしを支える一助になります。
>>【無料eBook】30代で知りたかった「お金」の極意 後悔しない8つのポイント
【オススメ記事】
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・独身男性の老後の生活費は?「一生ひとり」ならお金の準備はお早めに!
・時には遊び心も!テーマ型投資について
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・お金はありすぎてもダメ!?「限界効用の逓減」に見る幸せな億万長者の条件

