
「うちの会社の退職金、少なすぎるかもしれない……」
「中小企業の退職金相場って、実際いくらなんだろう?」
中小企業で働く多くの方が、将来の生活に漠然とした不安を抱えています。ニュースで見る大企業の退職金の額と比べて、自分の将来にため息をついている人も少なくないでしょう。
この記事は、そんなあなたのための「現実的な処方箋」です。
まず、最新の公的データに基づき、中小企業の退職金のリアルな相場と、大企業との間に存在する厳しい格差の理由を明らかにします。しかし、この記事の目的は不安にさせることではありません。
会社の制度だけに依存する時代が終わった今、正しい知識を武器に「じぶん退職金」を育てる方法を、具体的かつ実践的に解説します。国の節税制度の活用から、副業、そして毎月安定した収入を生み出す不動産投資まで、あなたに合った選択肢がきっと見つかります。
この記事を最後まで読めば、将来への漠然とした不安は「今日から何をすべきか」という明確な希望に変わるはずです。
目次
【結論】中小企業の退職金は「少ない」が、悲観は不要
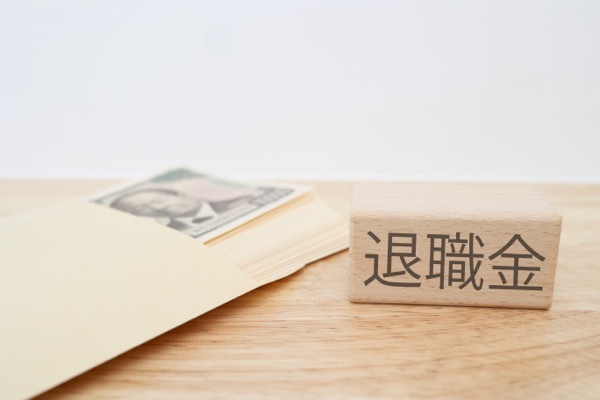
まず結論からお伝えします。あなたが感じている「うちの会社の退職金は少ないのではないか?」というその感覚は、残念ながら正しいです。
公的なデータを見ても、中小企業の退職金は大企業に比べて大幅に少ないという現実があります。
しかし、その事実を知って悲観する必要は全くありません。なぜなら、会社の退職金制度だけに老後のすべてを委ねるという時代は、とうの昔に終わっているからです。むしろ、この現実に早く気づけたことは幸運とさえ言えます。
これからの時代は、会社の制度を「老後資金のベース」と考え、それに自分自身で上乗せしていくのが当たり前になります。そして、そのための強力な武器(制度や方法)は、国によって、また民間のサービスとしてすでに用意されています。今から正しい知識で行動すれば、会社の規模に関係なく、あなた自身の手で豊かな老後資金を作り上げることは十分可能です。
なぜ?大企業と中小企業で退職金に1000万円以上の差がつく3つの理由

多くの人が抱く「なぜこんなに違うのか」という素朴な疑問。その背景には、個々の企業の努力だけでは埋めがたい、構造的な問題が存在します。この理由を理解することで、会社の制度に期待しすぎず、個人の力で備える必要性を論理的に納得できるはずです。
理由① 内部留保と収益性の違い
最も根本的な理由は、企業の体力、すなわち収益性と内部留保(企業の貯金)の差です。 大企業は長年にわたる事業で蓄積した豊富な内部留保を、社員の退職金の原資とすることができます。
一方、多くの中小企業は日々の運転資金や設備投資で手一杯であり、将来の退職金のために多額の資金を確保し続けるのが難しい、という現実があります。
理由② 退職金制度の普及率と種類の違い
そもそも、中小企業では退職金制度自体がないケースも珍しくありません。 東京都産業労働局の調査(令和4年)によれば、退職金制度がある企業は77.7%で、約2割の企業には制度がありません。また、制度があってもその種類に差があります。手厚い給付が期待できる「確定給付年金(DB)」や「退職一時金制度」は大企業が中心で、中小企業では後述する「中退共」など、比較的負担の軽い制度が選ばれる傾向にあります。
理由③ 人材戦略と福利厚生への考え方の違い
大企業にとって、手厚い退職金制度は優秀な人材を惹きつけ、長期間会社に定着させるための重要な「人材戦略」の一部です。 福利厚生を充実させることで、従業員のエンゲージメントを高める狙いもあります。
一方で、中小企業においては、人材確保は重要課題としつつも、まずは目の前の給与や賞与を優先せざるを得ず、退職金という遠い将来の福利厚生まで手が回らないのが実情です。
【年代・学歴別】中小企業の退職金、リアルな平均・相場はいくら?
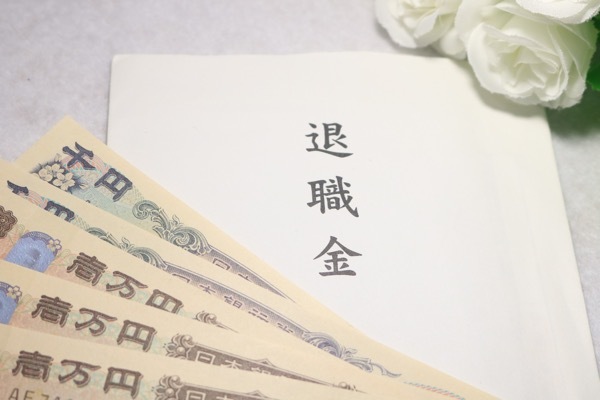
それでは、実際の中小企業の退職金はいくらなのでしょうか。ここでは、厚生労働省や東京都産業労働局の最新の調査結果を基に、具体的な平均額を見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせることで、将来の目標設定がより明確になります。
タイトルにもある「1149万円」は、東京都産業労働局の「令和6年 中小企業の賃金・退職金事情」における、大学卒・定年退職者のモデル退職金の平均額です。
▼勤続年数・学歴別のモデル退職金(自己都合退職の場合)
| 勤続年数 | 高校卒 | 高専・短大卒 | 大学卒 |
| 10年 | 985万円 | 102.1万円 | 112.5万円 |
| 20年 | 288.1万円 | 303.5万円 | 346.8万円 |
| 30年 | 575.7万円 | 582.2万円 | 750.7万円 |
| 定年(会社都合) | 974.1万円 | 992万円 | 1,149.5万円 |
一方、厚生労働省の調査によると、大企業を含む全体の平均退職給付額(定年退職者・大卒)は1,700万~2,200万円程度で推移しており、中小企業との間には1,000万円近い大きな差が存在することが分かります。
少ない退職金をカバーする「じぶん退職金」の作り方

厳しいデータを見て、改めて不安を感じたかもしれません。しかし、ここからが本題です。
会社の退職金はあくまで老後資金の「ベース」と考え、それに上乗せする『じぶん退職金』を今から作るのです。このポジティブな発想の転換が、あなたの未来を大きく変えます。これからご紹介する方法は、そのための具体的な武器です。
①【最重要・必須】国の最強節税制度「iDeCo」と「新NISA」をフル活用する
中小企業に勤務する方が、少ない退職金を補うためにまず活用すべきは、国の制度である「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「新NISA」です。 これらは、国が「自分の老後資金は自分で作ってください。その代わり税金を大幅に優遇します」というメッセージを込めて作った制度であり、使わない手はありません。
- iDeCo:最大のメリットは「掛金が全額所得控除になる」ことです。簡単に言えば、iDeCoに拠出した分だけ年収が低かったことになり、その年の所得税と翌年の住民税が安くなります。節税しながら、将来の年金を積み立てられる一石二鳥の制度です。
- 新NISA:最大のメリットは「運用で得た利益が全額非課税になる」ことです。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内であればそれが一切かかりません。
たとえば、月々3万円をiDeCoとNISAで20年間、年利5%で積み立て運用した場合をシミュレーションしてみましょう。
積立元本は720万円ですが、複利の効果で資産は約1,233万円にまで成長する可能性があります。通常の投資であれば利益(約513万円)に約102万円の税金がかかりますが、NISAなら非課税です。さらにiDeCoの掛金控除による節税額も加わります。これが国の制度の強力な効果なのです。
② 会社の制度を確認・活用する(中退共・企業型DC)
「自分の会社に退職金制度があるかどうかもよく分からない」という場合、まず就業規則の退職金規程を確認しましょう。また、給与明細に「確定拠出年金掛金」や「退職金共済掛金」といった項目がないかもチェックしてみてください。
中小企業で導入が多い制度として、「中退共(中小企業退職金共済)」と「企業型DC(企業型確定拠出年金)」があります。
- 中退共:会社が毎月掛金を積み立ててくれる制度です。従業員が直接何かをする必要は基本的にありませんが、自分が加入しているか、現在の積立額はいくらかを把握しておくことが重要です。
- 企業型DC:会社が掛金を拠出し、従業員自身が運用商品を選んで将来の退職金を育てる制度です。会社によっては、従業員が掛金を上乗せできる「マッチング拠出」が可能な場合もあります。これはiDeCoと同様に所得控除が受けられるため、利用できるなら積極的に活用しましょう。
③ 共済制度や財形貯蓄制度を利用する
会社によっては、これら以外の福利厚生制度が用意されている場合があります。代表的なものが「財形貯蓄制度」です。これは給与からの天引きで貯蓄ができる制度で、特に「財形年金貯蓄」は、貯蓄残高550万円までの利子などが非課税になるメリットがあります。iDeCoやNISAほどのインパクトはありませんが、着実に貯蓄できる手段として有効です。
④ 副業で収入源を増やす
iDeCoやNISAといった制度を活用するには、元手となる「種銭」が必要です。 その種銭を増やす最も現実的な手段が、副業で収入源を増やすことです。終身雇用が崩壊した現代において、収入源を複数持つことはリスク分散の観点からも非常に重要です。
特に40代、50代であれば、これまでのキャリアで培った経験やスキルそのものが商品になります。専門知識を活かしたコンサルティングや研修講師、Webサイト制作やライティングなど、オンラインで完結し、本業と両立しやすい副業から始めてみるのが良いでしょう。
⑤ 毎月安定収入を作る「不動産投資」という選択肢
iDeCoやNISAが資産を雪だるま式に「増やす」投資だとすれば、不動産投資は毎月お金を生み出す「じぶん年金」を作る投資です。本業で忙しい現役世代にこそ、検討してほしい有力な選択肢です。
- 少ない自己資金で始められる「レバレッジ効果」
不動産投資の最大の特徴は、銀行融資を活用できる「レバレッジ」にあります。少ない自己資金を元手に、数千万円という大きな資産を持てるのは、他の金融商品にはない魅力です。 - 安定した家賃収入(インカムゲイン)
入居者がいる限り、毎月決まった家賃収入が手に入ります。これは、公的年金や会社の退職金に上乗せできる、私的な年金そのものです。iDeCoやNISAのように資産を取り崩すのではなく、資産(不動産)を維持したまま継続的な収入を得られるのが大きな強みです。 - 生命保険の代わりになる
住宅ローンを組む際に加入する「団体信用生命保険(団信)」により、万が一オーナーに不幸があってもローンは完済され、家族には無借金の収益物件が残ります。これは、数千万円の生命保険に加入しているのと同じ効果があると言えます。 - 本業と両立しやすい
「物件の管理が大変そう…」と心配する方も多いですが、信頼できる管理会社に委託すれば、入居者募集から家賃回収、クレーム対応まで全て任せられます。オーナーがやることはほとんどなく、本業が忙しい方にこそ向いているのです。
⑥ 資産寿命を延ばす「守りの投資」も組み合わせる
iDeCoやNISAで積極的に資産を「増やす」ことと並行して、築いた資産を長持ちさせる「守る」視点も重要です。 これを「資産寿命を延ばす」と言います。そのための選択肢として、民間の「個人年金保険」や「高配当株投資」があります。
個人年金保険は、一定期間保険料を支払うことで、将来決まった額の年金を受け取れる商品です。大きなリターンは期待できませんが、将来のキャッシュフローを確定させられる安心感があります。
また、安定した大企業の株式の中から、高い配当金を継続的に出している銘柄に投資する高配当株投資も、定期的な収入(インカムゲイン)を得るための有効な手段です。
【年代別】今から始めて間に合う?40代・50代からの資産形成プラン
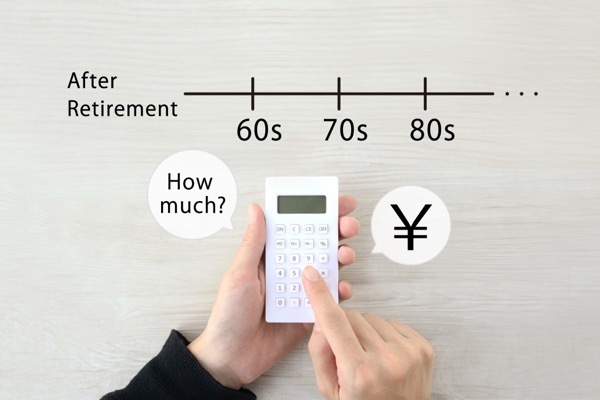
この記事を読んでいる方の中には、「もう40代、50代だから手遅れかもしれない……」という切実な不安を抱えている方も多いでしょう。しかし、決してそんなことはありません。年代ごとに最適な戦略を取ることで、今からでも未来は変えられます。
40代からの戦略:iDeCoとNISAを満額で15〜20年運用 + 不動産投資の検討
40代は、長期運用のメリットを享受できる「ラストチャンス」であり「ゴールデンエイジ」です。 60歳や65歳までにはまだ15〜20年という十分な運用期間が残されています。この期間を最大限に活かすため、iDeCoと新NISAの非課税メリットをフル活用し、全世界株式や米国株式のインデックスファンドなどにコツコツと長期で積み立てることが王道です。
同時に、不動産投資を始めるにも絶好のタイミングです。社会的信用度が高く、ローンの審査も通りやすい40代のうちに始めることで、退職までの期間でローン返済を進め、老後には安定した家賃収入を得る基盤を築くことができます。
50代からの戦略:リスクを抑えつつ、入金力を最大化 + 安定性重視の不動産投資
50代は運用期間が短くなるため、40代までとは戦略を変える必要があります。 リスクの高い株式などの割合を少しずつ減らし、元本確保型の商品や債券なども組み合わせた、守りを重視した資産形成へとシフトしていく時期です。それと同時に、役職定年などで収入が下がる前に「収入(入金力)を最大化」し、できるだけ多くの元本を確保することが最優先課題となります。
不動産投資においては、ローン期間は短くなりますが、自己資金の割合を増やしたり、空室リスクの低い都心の優良物件に絞ったりすることで、より安定性を重視した運用が可能です。退職金の一部を頭金にして、キャッシュフローの厚い物件を購入するという出口戦略も視野に入ります。
会社の退職金に期待せず、今日から「じぶん退職金」作りを始めよう

中小企業の退職金が少ないというのは、残念ながら変えようのない事実です。しかし、それに嘆いていてもあなたの老後資金は1円も増えません。重要なのは、事実を冷静に受け止め、今日から自分自身で行動を起こすことです。
この記事の要点を再確認しましょう。
- 中小企業の退職金相場は、大卒・定年で平均約1,149万円。大企業とは1,000万円以上の差がある。
- 会社の制度に期待しすぎず、「じぶん退職金」を作るという発想が不可欠。
- そのための最強の武器は、国の優遇制度である「iDeCo」と「新NISA」。これは全員が必須で取り組むべき。
- iDeCoやNISAと並行し、安定した私的年金を作る「不動産投資」も極めて有力な選択肢。
- 自分の会社の退職金制度(中退共や企業型DCなど)を確認し、活用できるものは漏らさず活用する。
将来への不安を感じているだけでは、何も変わりません。今日、この記事を読んだあなたが取るべき最初の、そして最も重要な行動は、難しい投資の勉強をいきなり始めることではありません。
まずは、ネット証券のサイトで「iDeCo」や「新NISA」の資料を請求してみること。会社に資産形成に役立つ制度がないか問い合わせてみること。そして、「不動産投資」に興味があるなら、信頼できる会社が開催する無料のオンラインセミナーに参加してみるのもいいでしょう。
そのわずか数分の行動が、あなたの10年後、20年後の未来を大きく変える第一歩となるのです。
>>【無料eBook】30代で知りたかった「お金」の極意 後悔しない8つのポイント
【オススメ記事】
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・独身男性の老後の生活費は?「一生ひとり」ならお金の準備はお早めに!
・時には遊び心も!テーマ型投資について
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・お金はありすぎてもダメ!?「限界効用の逓減」に見る幸せな億万長者の条件

