
「将来のために、今からお金を増やしたいけど、何から始めたら良いか分からない……」そう考えている人に、初心者でも始めやすい方法を、編集部が独自の基準により作成したランキングをもとに紹介します。
ランキングの軸は3つで、「リスクの低さ」「始めやすさ」と「期待リターン」から総合的に評価しています。特に、投資初心者が挫折せず、安心して第一歩を踏み出せるよう、「始めやすさ」と「リスクの低さ」を優先し、その上で「期待リターン」を加味して、順位付けを行いました。
本業で忙しい現役世代でも、無理なく始められる方法を選んでいますので、ぜひ参考にしてください。
目次
「お金を増やす方法」ランキングTOP10

1位 投資信託(インデックスファンド)──資産形成の王道。リスク抑えコツコツ投資を
【評価】
リスクの低さ ◎
始めやすさ ◎
期待リターン 〇
【評価理由】
「始めやすさ」「リスクの低さ」共に最高評価。期待リターンも十分見込めるため、資産形成の第一歩として。
投資信託(インデックスファンド)は、まさに資産形成の王道で、少額から始められ、自動的に分散投資されるため、リスクを抑えながら、長期で資産を増やすには欠かせない商品です。
インデックスファンドは、日経平均株価やS&P500などの特定の指数に連動するように運用されるため、個別の企業分析をする必要がありません。また、個別企業の株をそれぞれ買わなくて済むため、コストも抑えられます。人気の「オルカン」も、全世界の株式市場の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドの一種です。
インデックスファンドへの投資をするなら、NISAやiDeCoといった非課税になる制度を使えば、運用益が非課税になるため、さらに効果的に資産を増やせます。
NISAのつみたて投資枠や、クレカ積立の仕組みを使って毎月コツコツ買えば、価格変動リスクを抑えながら、手間なく長期的な資産形成を目指せるため、本業が忙しい現役世代の方にも非常におすすめです。
なお投資信託の中には、日経平均などの特定の指数に連動するインデックスファンドのほか、ファンドマネージャーというプロが運用先を決めるアクティブファンドなどもあります。
投資信託には、販売手数料のかからないノーロードのファンドも多数あります。投信を選ぶ際には、コストの低さを意識しましょう。
2位 ロボアドバイザー──投資先を選んでくれる手軽なサービス
【評価】
リスクの低さ ◎
始めやすさ ◎
期待リターン 〇
【評価理由】
評価は1位とほぼ同じだが、自分で選ぶ手間すらないため、知識ゼロでも始められる「究極の手軽さ」が特徴。
ロボアドバイザーは、事前に質問に答えるだけで、AIがリスク許容度や目標に合わせた最適なポートフォリオを提案・運用してくれるサービスです。購入した商品の価格が大きく動いた後には、全体のバランスを定期的に見直して調整してくれる機能もあるため、投資を始めたら”ほったらかし”にしておきたい人に向いています。
有名なところでは、WealthNavi(ウェルスナビ)やTHEO(テオ)などが知られていますが、それぞれ手数料や最低投資額、機能が異なるので、自分のライフスタイルや目標に合ったサービスを選びましょう。証券会社が用意しているサービスもあります。
3位 個人向け国債(変動10年)──増やすより減らさないことが重要なら
【評価】
リスクの低さ ◎
始めやすさ 〇
期待リターン ×
【評価理由】
元本保証という「究極の安全性」を持つ商品。「投資=怖い」というイメージを払拭し、「絶対に損をしない」体験をするための最初のステップに。期待リターンは4位の債券ファンドよりも低いが、リスクの低さなどから上位に。
「投資で資産を減らすのが怖い」「大きく増やさなくていい」という人は、個人向け国債(変動10年)をポートフォリオに入れるとよいでしょう。国が元本と利息の支払いを保証しているため、金融商品の中ではリスクが低いと言えますが、半年ごとに金利が見直される変動金利型のため、将来の金利上昇にも対応できます。
個人向け国債の魅力は、最低1万円から購入でき、証券会社や銀行など身近な金融機関で手軽に申し込める点です。発行から1年経過すれば、中途換金もできるので、急な資金が必要になった場合でも安心です。安全性を最優先し、投資の第一歩を踏み出したい方にとって、安心して「絶対に損をしない」体験を積むための最適な選択肢と言えるでしょう。
なお個人向け国債には変動10年のほか、固定金利の3年と5年もあります。
参考:個人向け国債(財務省)
4位 債券ファンド(債券ETF)──株式よりも元本割れリスク低め NISAでも投資可
【評価】
リスクの低さ ◎
始めやすさ 〇
期待リターン △
【評価理由】
個人向け国債と同様にリスクが極めて低い選択肢。国債よりリターンが期待できるため、守りの資産の中でも少しだけ成長を意識したいなら。
債券は、お金を借りたい企業や政府、地方公共団体などが発行するもので、債券を買った投資家は、これを満期まで保有すれば元本が償還されるため、株式投資に比べて元本割れのリスクが低いと言えます。満期に償還金を受け取れるほか、満期までの期間も定期的に利息が支払われます。
債券ファンドや債券ETFは、株式に比べて価格変動が激しくないと言え、守りの資産として非常に有効です。ポートフォリオ全体の安定性を高めることができます。
少額から投資できる商品も多く、ETFであれば株式のようにリアルタイムで売買することもできます。なおNISAでは債券は買えませんが、成長投資枠なら債券ファンドが買えるほか、債券を含むバランスファンドならつみたて投資枠でも買えます。
5位 J-REIT(不動産投資信託)──少額から不動産投資できる
【評価】
リスクの低さ 〇
始めやすさ 〇
期待リターン 〇
【評価理由】
少額から始められ、バランスが取れたミドルリスク・ミドルリターンの代表格。資産成長のステージの入り口として最適。
J-REIT(不動産投資信託)は、実際の不動産を購入するわけではなく、不動産を保有・運用する会社に投資する商品で、現物不動産投資に比べて少額で、手軽に始められます。複数の物件に分散投資されているため、リスクも分散されやすく、賃料収入を原資とした分配金(配当)が期待できる点が魅力です。
J-REITには、オフィスビル、商業施設、ホテル、住宅など、様々な種類の不動産に投資する銘柄があります。少額から不動産オーナー気分を味わえ、専門家が物件の選定から管理まで行ってくれるため、不動産投資の知識がなくても始めやすいでしょう。
一般的に、「ミドルリスク・ミドルリターン」に分類される商品で、分散投資の一環としてポートフォリオに加えることで、安定した収益と資産の成長の両方を期待できます。
6位 金(ゴールド)──安全資産の代表格 ETFなどで少額購入も可
【評価】
リスクの低さ 〇
始めやすさ 〇
期待リターン △
【評価理由】
J-REITと同様に「始めやすさ」「リスクの低さ」は「〇」。期待リターンがやや劣るが、ポートフォリオの安定化に貢献する重要な選択肢。
金(ゴールド)は、有事の際に価値が上昇しやすい「安全資産」としての代表格で、株式や債券とは異なる値動きをするため、ポートフォリオに組み入れることで、全体の安定性を高める効果が期待できます。
特に、インフレ対策としても有効とされており、通貨の価値が下がった際に金の価値が相対的に上昇する傾向があります。
現物購入のほか、純金積立や金ETFなど様々な方法で投資でき、少額からでも始められます。純金積立であれば、毎月一定額を積み立てることで、ドルコスト平均法の効果も期待できます。大きなリターンは期待しにくいものの、資産を守るという意味で重要な役割を果たす選択肢です。
特に、株式などのリスク資産の割合が高いポートフォリオにおいて、金の組み入れはリスク分散に貢献します。
7位 現物不動産──相続対策にも!長期で資産を守りたいなら
【評価】
リスクの低さ △
始めやすさ ×
期待リターン 〇
【評価理由】
一般的に「ミドルリスク・ミドルリターン」に分類され、安定した家賃収入が期待できるが、自己資金と専門知識が必須で、「始めやすさ」は高くない。
現物不動産投資は、アパートやマンションなどを実際に購入し、家賃収入を得る投資方法で、相続税対策や生命保険代わりに使う方法もあるので、ある程度の規模の自己資金や、土地が既にあり、資産を守りたい、相続を見越して長期で運用したいという人に向いています。
魅力は安定した家賃収入(インカムゲイン)と、将来、不動産価格が上がった際に売れば売却益(キャピタルゲイン)が期待できることです。
ただし注意点としては、一般に多額の自己資金が必要で、物件管理の手間や空室リスク、修繕費などのコストもかかります。不動産に関する専門知識や、金融機関からの融資に関する知識も必須となるため、投資初心者が始める際のハードルは非常に高いと言えます。
とはいえ、不動産投資のアドバイスや物件紹介をしてくれるサービスも多く、サラリーマンをしながら大家になっている人も少なくありません。本業の定期収入があるサラリーマンならローンも組みやすいため、興味があるなら検討してみてはいかがでしょうか。
78位 高配当株──継続的な配当収入を狙えるが、銘柄選定する知識が必要
【評価】
リスクの低さ △
始めやすさ △
期待リターン ◎
【評価理由】
8位以下は上級者向け。個別銘柄を選ぶ知識と、それに伴うリスクを取る必要があります。
高配当株は、安定して高い配当を出す企業の株式のことで、継続的な配当収入を得ることを目的とした投資対象です。一般的に、利回り4%以上の銘柄のことを高配当株と呼ぶことが多いようです。特に、NISA口座を活用すれば、売却益だけでなく配当金も非課税になるため、手取り額を増やせます。
しかし、個別銘柄を選ぶには、企業の財務状況や将来性、配当政策などを詳しく見極める知識が必要です。企業の業績悪化などにより減配や無配になるリスクもあり、株価が下落して元本割れを起こす可能性もゼロではありません。
キャッシュフローを重視する経験者向けの選択肢であり、上級者向けの投資と言えるでしょう。
89位 米国株式(個別株)──世界的に有名な企業の成長の恩恵を狙う
【評価】
リスクの低さ ×
始めやすさ △
期待リターン ◎
【評価理由】
「リスクの低さ」が「×」の、ハイリスク・ハイリターン投資。高いリターンが魅力ですが、大きな損失を被る可能性も。
米国株式(個別株)には、GAFAM(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)に代表されるようなグローバル企業など世界経済を牽引する成長企業が多く、その成長の恩恵を受けられる可能性があります。外国の中でも米国の企業や市場については、情報収集もしやすく、日中の取引も可能な証券会社も増えています。
しかし、その分リスクも高く、企業の業績や市場の変動によっては大きな損失を被る可能性も十分にあります。一般に日本円から米ドルに替えて投資するため、為替変動リスクも考慮する必要があります。高いリターンが期待できる商品は、それだけリスクも大きいことを覚えておきましょう。
9位 現物不動産──相続対策にも!長期で資産を守りたいなら
【評価】
リスクの低さ △
始めやすさ ×
期待リターン 〇
【評価理由】
一般的に「ミドルリスク・ミドルリターン」に分類され、安定した家賃収入が期待できるが、自己資金と専門知識が必須で、「始めやすさ」は高くない。
現物不動産投資は、アパートやマンションなどを実際に購入し、家賃収入を得る投資方法で、相続税対策や生命保険代わりに使う方法もあるので、ある程度の規模の自己資金や、土地が既にあり、資産を守りたい、相続を見越して長期で運用したいという人に向いています。
魅力は安定した家賃収入(インカムゲイン)と、将来、不動産価格が上がった際に売れば売却益(キャピタルゲイン)が期待できることです。
ただし注意点としては、一般に多額の自己資金が必要で、物件管理の手間や空室リスク、修繕費などのコストもかかります。不動産に関する専門知識や、金融機関からの融資に関する知識も必須となるため、投資初心者が始める際のハードルは非常に高いと言えます。
とはいえ、不動産投資のアドバイスや物件紹介をしてくれるサービスも多く、サラリーマンをしながら大家になっている人も少なくありません。本業の定期収入があるサラリーマンならローンも組みやすいため、興味があるなら検討してみてはいかがでしょうか。
10位 日本株式(個別株)──銘柄選定は難しい 投信や1株投資から始めるのも手
【評価】
リスクの低さ ×
始めやすさ △
期待リターン 〇
【評価理由】
米国株と同様にハイリスク。期待リターンでやや劣るため、最下位。
日本株式(個別株)投資は、米国株と同様に、比較的ハイリスク・ハイリターンな投資と言えますが、外国企業と比べて情報収集がしやすい、身近な企業の株を買えるため、投資をより身近に感じられるといった特徴・メリットもあります。
上場企業の中には株主還元、具体的には配当や優待を充実させているところも多いため、優待や配当目当ての投資も注目されています。
ただし、企業には倒産する可能性もありますし、不動産や債券などと比べると価格の変動幅が大きいなど、こうした注意点を十分把握しておきたいところです。
なお、同じ個別株投資でも、米国株と比べると期待リターンでやや劣るため、ランキングでは下位の評価となりました。
日本の企業への投資を考えているなら、まずは投資信託やロボアドバイザーに投資する、もしくは、1株などごく少ない数量から投資するなど、リスクを抑えながら始めるとよいでしょう。
| 順位 | 商品 | リスクの低さ | 始めやすさ | 期待リターン |
| 1 | 投資信託(インデックスファンド) | ◎ | ◎ | 〇 |
| 2 | ロボアドバイザー | ◎ | ◎ | 〇 |
| 3 | 個人向け国債 | ◎ | 〇 | × |
| 4 | 債券ファンド(債券ETF) | ◎ | 〇 | △ |
| 5 | J-REIT(不動産投資信託) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 金(ゴールド) | 〇 | 〇 | △ |
| 7 | 現物不動産 | △ | × | 〇 |
| 78 | 高配当株 | △ | △ | ◎ |
| 89 | 米国株式(個別株) | × | △ | ◎ |
| 9 | 現物不動産 | △ | × | 〇 |
| 10 | 日本株式 | × | △ | 〇 |
資産運用を加速させるには税制優遇の仕組みを活用しよう
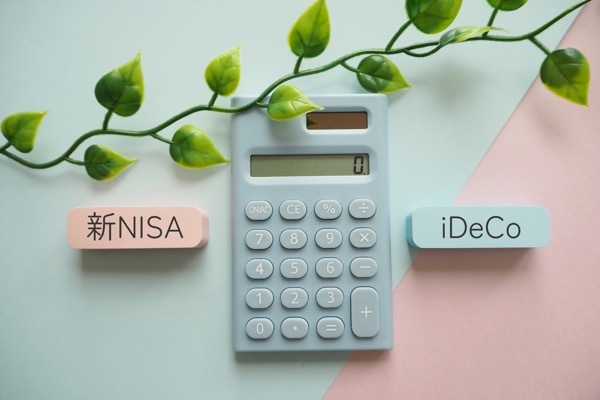
資産運用で効率的にお金を増やしていくためには、ただ投資するだけでなく、税金対策も非常に重要で、まず検討したいのは2つの税制優遇制度、「NISA」と「iDeCo」です。これらの制度を上手に使うことで、運用益にかかる税金を抑え、より効率的に資産を増やせます。
制度① NISA 投信や株への投資で活用したい
NISA(ニーサ)は、少額投資非課税制度のことで、投資で得た利益が一定の金額まで非課税になるお得な制度です。
通常、株式や投資信託などの売買益や配当金には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で運用すればこの税金がゼロになります。2024年から新NISAとして制度が大幅に拡充され、非課税保有限度額が最大1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)、年間投資枠も360万円に拡大され、非課税保有期間も無期限になりました。
NISAで投資できる商品は幅広く、ランキングで1位に挙げた「投資信託(インデックスファンド)」はもちろんのこと、8位の「高配当株」や10位の「日本株式(個別株)」、9位の「米国株式(個別株)」、さらには5位の「J-REIT(不動産投資信託)」も対象です。つみたて投資枠では、長期・積立・分散投資に適した投資信託を選べ、成長投資枠ではより多くの種類の投資信託や株式に投資できます。
特に、非課税投資枠が大きく、非課税期間が無期限になったことで、長期的な資産形成において非常に強力なツールとなっています。
参考:NISAを知る(金融庁)
制度② iDeCo 60歳まで引き出さない資金は
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、自分で運用する私的年金制度で、NISAと同様に運用益が非課税になるだけでなく、NISAにはない特徴も備えています。
iDeCoならではの大きなメリットは3つあります。1つ目は、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されること、2つ目は、運用益が非課税になること、そして3つ目は、受け取る際にも税制優遇があることです。この3つの税制メリットは、iDeCoの大きな強みと言えるでしょう。
一方で、デメリットとしては、原則60歳まで資金を引き出すことができない点や、口座管理手数料がかかる点が挙げられます。NISAが比較的自由に資金の出し入れができるのに対し、iDeCoは老後資金の形成に特化した制度であるため、流動性が低い点に注意が必要です。
しかし、その分、税制優遇が手厚く、長期的な視点で老後資金を準備するには非常に有効な制度です。iDeCoでは、ランキングでも紹介した債券ファンドやJ-REITなどの投資信託も選択肢に含まれるため、NISAと組み合わせて活用することで、より多様なアセットクラスに投資し、効率的に資産形成を進めることができます。
NISA・iDeCoを活用した年代モデルポートフォリオ
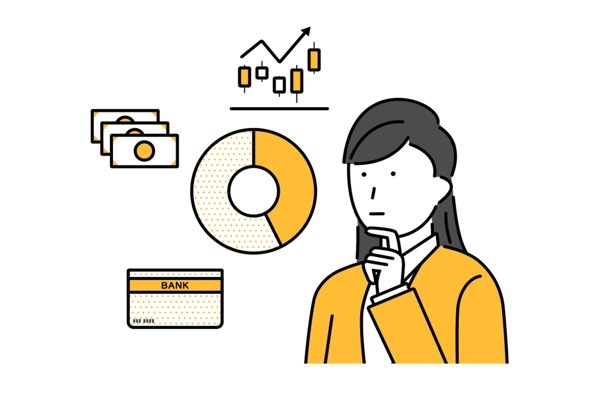
資産運用は、年代やライフステージによって最適な戦略が異なります。NISAとiDeCoを効果的に活用した、年代別のモデルポートフォリオの概要を見ていきましょう。
【20代】NISAで全世界株式インデックス100%の積極運用
20代は、投資期間を長く確保できるため、多少のリスクを取ってでも大きなリターンを狙う積極的な運用がおすすめです。NISAのつみたて投資枠を活用し、全世界株式インデックスファンドに厚めに投資する戦略は、世界の経済成長の恩恵を最大限に享受できる可能性を秘めています。
ドルコスト平均法により、高値掴みのリスクを抑えながら、長期的な視点で資産を大きく育てていくことが期待できます。
【30代】NISAとiDeCoを併用したバランス型運用
30代になると、結婚や出産、住宅購入など、ライフイベントが増え始める時期なので、NISAとiDeCoを併用し、リスクとリターンのバランスを取った運用にシフトしていくのがよいでしょう。
たとえばNISAでは引き続き株式中心の投資信託で資産の成長を狙いつつ、iDeCoでは債券ファンドなども組み入れるなどして、ポートフォリオ全体の安定性を高めます。老後資金の準備も視野に入れ、バランスの取れた資産形成を目指しましょう。
【40代】守りも意識した安定成長ポートフォリオ
40代は、資産の「守り」も意識し始める時期です。NISAでは引き続き成長を狙いつつも、iDeCoでは債券やJ-REITの比率を少しずつ高めて、リスクを抑えた安定成長を目指します。
ある程度、資産ができていれば、現物不動産投資も検討するのもよいでしょう。ただし、資金と専門知識が必要なため、慎重に検討することが重要です。
無理のない範囲でリスクをコントロールし、着実に資産を増やすことを意識しましょう。
【50代以降】「守り」を最優先し、資産寿命を延ばす運用
50代以降は、定年が近づき、資産を取り崩して生活する時期が視野に入るため、「守り」を最優先し、資産寿命を延ばす運用にシフトしていくことが重要です。
NISAでは安定性の高い投資信託や債券ファンドの比率を高め、iDeCoでは元本割れのリスクが極めて低い個人向け国債などを組み入れるのもよいでしょう。
一気にリスクの高い投資に手を出すのは避け、慎重に資産を守りながら、計画的に資産を取り崩していく準備を進めましょう。
投資を始める前に必ずやるべき3つの準備

資産運用を成功させるためには、やみくもに始めるのではなく、事前の準備が非常に重要です。投資を始める前に必ずやっておきたいことが3つあります。
1. 投資目的と目標金額の明確化
なぜ投資をするのか、その目的を明確にしましょう。
たとえば、「老後の生活資金を2,000万円準備したい」「教育資金として500万円貯めたい」など、具体的な目的と目標金額を設定することで、どのような商品を選び、どのくらいの期間運用すれば良いのかが明確になります。
目的が明確であれば、途中で市場が変動しても一喜一憂することなく、冷静に投資を続けられます。
2. リスク許容度の確認
投資にはリスクがつきものなので、自分がどの程度の損失なら許容できるのか、リスク許容度を事前に確認しておくことが非常に重要です。
元本が保証されない商品に投資する際には、最悪の場合、元本をすべて失う可能性も考慮に入れる必要があります。リスク許容度を超えた投資は、精神的な負担が大きくなり、冷静な判断ができなくなる原因となります。
無理のない範囲で投資を行うためにも、事前に自分のリスク許容度を把握しておきましょう。
3. 生活防衛資金と余裕資金の準備
投資は、失っても生活に支障のない「余裕資金」で行うのが鉄則です。万が一の病気や失業などに備える「生活防衛資金」として、最低でも生活費の3~6ヵ月分はすぐに使える預貯金で確保しておきましょう。その額は、預貯金の額や保険への加入状況、扶養する家族の数などによります。
いずれにせよ、この生活防衛資金は、投資資金とは明確に区別し、決して手をつけないようにしてください。生活防衛資金を確保した上で、初めて余裕資金を投資に回すようにしましょう。
投資でお金を増やす上で絶対に知っておくべき注意点

投資でお金を増やすためには、ただ商品を選ぶだけでなく、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。これらを知らずに投資を始めると、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。
「元本保証で高利回り」は100%詐欺と心得る
「元本保証で高利回り」をうたう投資話には絶対に手を出してはいけません。このような話は、ほとんどが詐欺であると心得ましょう。
投資には必ずリスクが伴い、高いリターンを期待できる商品ほど、リスクも高くなるのが一般的です。リスクゼロで高利回りという金融商品は存在しないことを肝に銘じ、安易な儲け話には乗らないように注意しましょう。
「長期・積立・分散」の基本原則を徹底する
投資の基本原則は、「長期・積立・分散」です。長期投資は、時間の経過とともに複利効果を最大化し、短期的な市場の変動リスクを吸収します。
積立投資は、定期的に一定額を投資することで、高値づかみのリスクを軽減し、ドルコスト平均法の恩恵を受けられます。分散投資は、複数の資産や地域に分けて投資することで、特定のリスクが全体に与える影響を小さくします。
これらの原則を徹底することで、リスクを抑えながら着実に資産を増やす可能性が高まります。
短期的な市場の変動に一喜一憂しない
投資をしていると、日々の市場の変動に不安を感じたり、利益が出るとすぐに売却したくなったりするものですが、短期的な値動きに惑わされず、一度決めた方針を頻繁に変えないようにしましょう。
短期的な市場の動きに一喜一憂して売買を繰り返すことは、かえって損失を拡大させたり、機会損失を招いたりする原因となるからです。
利益が出た場合の税金と確定申告を理解する
NISAやiDeCoのような非課税制度を活用しない場合、投資で得た利益には税金がかかるので、税金に関する知識も身につけておくことで、安心して投資を続けられます。
たとえば、株式や投資信託の売却益や配当金には、原則として約20%の税金が課せられます。特定口座(源泉徴収あり)を選べば、証券会社が税金を計算して徴収してくれるため、原則として確定申告は不要ですが、一般口座を利用している場合や、他社口座での取引と損益を通算させたい場合は、確定申告する必要があります。
最適な商品と制度を組み合わせ、今日から第一歩を

お金を増やす方法としておすすめの金融商品をランキング形式にし、さらにNISAやiDeCoといった税制優遇制度の活用法、年代別のモデルポートフォリオ、そして投資を始める上での注意点までを幅広く解説しました。
お金持ちではないけれど、生活に多少の余裕があり、副業や資産運用・資産形成を考えている現役世代にとって、無理なく不労所得を目指すためには、「始めやすさ」と「リスクの低さ」を重視した商品選びと、税制優遇制度の活用が非常に重要です。
特に、ランキング上位の投資信託(インデックスファンド)やロボアドバイザーは、時間のない方でも手軽に始められるため、資産形成の第一歩として最適です。また、ある程度資金や投資の経験・知識ができたら、現物不動産などを活用した運用を検討することで、効率的に資産形成ができます。
「長期・積立・分散」という投資の基本原則を守りながら、自分の投資目的、目標金額、リスク許容度に合わせて最適な商品と制度を組み合わせましょう。早いうちに小さな一歩を踏み出すことが、将来の豊かな生活へとつながります。
>>【無料eBook】30代で知りたかった「お金」の極意 後悔しない8つのポイント
【オススメ記事】
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・独身男性の老後の生活費は?「一生ひとり」ならお金の準備はお早めに!
・時には遊び心も!テーマ型投資について
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・お金はありすぎてもダメ!?「限界効用の逓減」に見る幸せな億万長者の条件

