
トランプ米大統領による相互関税の発表で世界同時株安となり、株式市場は大きな変動を繰り返しています。これまで「NISA(少額投資非課税制度)」を中心に資産形成を進めてきた人たちの中には、将来への不安を感じ始めている方も多いのではないでしょうか。
たしかに、NISAは優れた制度ではありますが、それだけに頼ることには限界もあります。
本記事では、NISA以外で活用できる資産形成の選択肢を幅広く紹介し、それぞれの特徴やリスクについて中立的に整理していきます。そしてその中でも、不動産投資がいま再評価されている理由についても取り上げ、これからの資産形成を考えるうえでのヒントを提供します。
目次
1.NISAだけではリスクがある

これまでの資産形成では、「NISA」や「iDeCo」といった制度が注目されてきました。時間を味方につけてコツコツ積み立てるスタイルは、初心者にとっても始めやすく、一定の成果も上げてきた方もいるでしょう。
しかし2025年現在、世界の経済環境が急速に変化する中で、こうした制度だけに依存する資産形成にはリスクがあることが、徐々に明らかになってきています。
1-1.非課税制度の枠には限界がある
NISAやiDeCoの魅力は、運用益が非課税になることです。2024年に新NISA制度がスタートし、より使いやすくなった一方で、それでもこれらの制度には金額や商品に関する制限があります。
| 制度 | 年間投資枠 | 対象商品 |
|---|---|---|
| NISA(つみたて投資枠) | 年120万円 | 長期積立に適した一定の投資信託など |
| NISA(成長投資枠) | 年240万円 | 株式やETFなども含まれる |
| iDeCo | 年14.4〜81.6万円 | 投資信託・定期預金など(職種で上限変動) |
これらの非課税枠だけでは、将来のインフレやライフイベントに備えるには運用できる金額として十分とはいえないという課題もあります。また、NISAはいつでも売却できますが、iDeCoは原則60歳まで引き出し不可という流動性の面でも注意が必要です。
1-2.投資信託のメリットと落とし穴
非課税制度の中核をなす「投資信託」も万能ではありません。たしかに、金融リテラシーが高くなくても始めやすい投資商品ではありますが、そこには見落とされがちなリスクも存在します。
1-2-1.投資信託のメリット
・分散投資ができる:複数の資産に自動的に分散されることでリスクが抑えられる
・少額から始めやすい:毎月1,000円程度からでも投資可能
・自動積立で手間いらず:設定さえしておけば“ほったらかし”で資産形成ができる
1-2-2.投資信託のデメリット
・相場の影響を受ける:複数の株式や債券に分散されていても、世界的な金融ショックの影響は免れない
・信託報酬などの手数料が継続的にかかる:数%の手数料がパフォーマンスを下げる要因に
・元本保証がない:運用成績によっては元本割れのリスクも当然ある
こうしたメリット・デメリットを把握したうえで、投資信託を「選択肢の一つ」として位置付けることが重要です。
1-3.ポートフォリオ設計や分散投資が重要
NISAやiDeCoだけに頼る資産形成が危ういとすれば、次に考えるべきは「では、どう備えるべきか?」という問いです。そこでカギになるのが、“分散投資”と“ポートフォリオ設計”という考え方です。
投資を一つの手段に絞るのではなく、複数の性質を持つ資産を組み合わせて保有することで、リスクを抑えながら安定した成果を目指す。このアプローチは、世界中の機関投資家や富裕層も実践している、資産防衛の基本戦略ともいえます。
1-3-1.「異なるリスクの資産」を組み合わせる意味
たとえば、株式と債券は一般的に逆の動きをすることが多いとされています。株価が下落する局面では、リスクを嫌った投資家が債券に資金を移し、価格が上がる——そんな関係性があるからです。
同様に、不動産や金(ゴールド)は、株式や債券と相関の低い動きをする資産クラスです。
つまり、価格が一斉に下がるリスクを避けやすいというメリットがあるわけです。
このように、「異なる動きをする資産」を組み合わせることで、どれか一つが大きく下がっても、他が支えてくれる構造をつくることができます。これが分散投資の本質です。
1-3-2.自分のリスク許容度に応じた配分設計が鍵
もう一つ大切なのが、自分自身のリスク許容度に応じた資産配分を考えることです。年齢、家族構成、収入の安定性、投資経験、ライフイベントの有無——これらによって、「どこまでリスクを取れるか」「どれくらい守りを厚くするべきか」は人それぞれ異なります。
たとえば、20〜30代で長期的なリターンを狙いたい人なら、株式や不動産の割合を多めに。一方で、50代以降で資産を守りながら運用したい人は、債券や現金比率を高めにする、というような配分が考えられます。
投資において「万人に最適な正解」はありません。だからこそ、自分にとって無理のない配分=納得できるポートフォリオを持つことが、資産形成を続けるうえで最も大切なポイントなのです。
2.NISA以外の資産形成方法と、それぞれの特徴まとめ

資産形成を考える際、NISAやiDeCoは非常に優れた制度ですが、世界経済の変化や自分自身のライフステージに応じて、複数の資産を組み合わせていく視点も欠かせません。どの投資手段にも、それぞれ特有のメリットとデメリットがあり、当然ながらリターンにはリスクが伴います。
ここでは、NISA以外にも活用できる主要な投資手段を取り上げ、それぞれの特徴や向き・不向きを中立的な視点で整理していきます。自分に合った選択肢を見極めるための比較材料として、参考にしていただければ幸いです。
2-1.投資信託(NISA口座以外)
NISAを活用して投資信託を積み立てている人も多いですが、NISA口座の枠を超えて、課税口座でも投資信託を継続しているという人は少なくありません。投資信託は、初心者にも比較的ハードルが低く、手軽に始められる金融商品です。投資信託にはどのような特徴があるのか。ここでは、そのメリットとデメリットを整理しておきます。
2-1-1.投資信託のメリット
・分散投資によりリスクを抑えやすい
一つの投資信託で複数の銘柄(株式・債券など)に分散投資されており、市場の一部が下落しても全体への影響が緩和されやすい構造です。
・自動積立が可能で初心者にも始めやすい
金融機関の設定により、毎月一定額を自動で積み立てることができるため、投資経験が少ない人でも始めやすいのが特徴です。
・少額からスタートできる
1,000円単位など、比較的少額から投資できるため、気軽に余剰資金で投資することが可能です。
2-1-2.投資信託のデメリット
・信託報酬などの手数料が継続的に発生
多くの投資信託では、運用中に年率0.1〜1%程度の信託報酬が発生します。長期投資ではこのコストが意外に重くのしかかることもあります。
・相場全体の影響を受けやすい(元本保証なし)
投資信託は、投資対象となる株式や債券の価格に連動するため、景気や世界経済の変動により元本割れする可能性も否定できません。
・リターンに対する実感が薄く、途中解約もしづらい場合がある
ファンドの値動きが緩やかであればあるほど、資産が増えている実感が持ちにくくなります。さらに、解約タイミングによっては損失を抱えることもあり、心理的に継続が難しくなる場面もあります。
2-2.個別株式投資(国内/米国株)
資産運用と聞いて「株式投資」を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。
実際、企業の成長に直接投資できる株式は、資産を大きく増やす可能性を持つ投資手段の一つです。国内株・米国株ともに選択肢が広がり、NISA枠外でも活用している投資家は少なくありません。
ただし、株式投資には相応の知識とリスク管理も求められます。ここでは、そのメリットと注意点を整理してみましょう。
2-2-1.株式投資のメリット
・銘柄選定次第で高いリターンが期待できる
成長企業や割安株に投資することで、株価が大きく上昇し、短期間で資産が大きく増えることもあります。
・配当金や株主優待を受け取ることができる
配当金のある銘柄は長期保有をすることで、定期的な配当収入を得ることができます。日本株では、個人投資家向けに設定された株主優待制度も個別銘柄に投資する大きなメリットです。
・リアルタイムで売買可能(流動性が高い)
株式は取引所が開いていればいつでも売買できるため、現金化のしやすさ(流動性)において他の資産に比べて優れています。
2-2-2.株式投資のデメリット
・価格変動が大きく、損失リスクも高い
市場のニュースや企業業績に大きく反応するため、短期間で大幅に価格が変動することも少なくありません。特に個別銘柄に集中して投資している場合、リスクも高まります。
・情報収集やタイミング判断が必要
銘柄選定には、業績・財務・成長性・経営陣の質などの分析が必要です。また、「いつ買っていつ売るか」のタイミング判断も成績に大きく影響します。
・感情で判断すると大きな失敗につながる
株価の上げ下げに一喜一憂し、「怖くなって損切り」「焦って高値掴み」といった判断ミスを誘発しやすいのも株式投資の特徴です。冷静さを保つことが求められます。
株式投資はリターンを狙いたい人にとって魅力的な選択肢ですが、それと同時に「知識・分析力・メンタルコントロール」が求められます。
2-3.iDeCo・企業型DC(年金対策)
老後資金を準備するための制度として、NISAと同様に人気を集めているのがiDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)です。いずれも、拠出したお金を自ら運用し、将来の年金として受け取る制度であり、長期の資産形成に向いた選択肢といえます(日本版401kとも呼ばれます)。
特にiDeCoは、公務員や会社員、自営業者など幅広い層に開かれた制度として広がりを見せており、節税効果の高さが大きな魅力となっています。一方で、自由度や流動性の面では注意も必要です。以下に、iDeCoを中心とした年金制度のメリットとデメリットを整理します。
2-3-1.iDeCoのメリット
・掛金が全額所得控除される(節税効果が大)
毎月の掛金が「所得控除」となり、課税所得を減らせるため、年収の高い人ほど節税効果が大きくなります。
・運用益も非課税で複利効果が得やすい
通常の投資で発生する売却益や分配金への課税がゼロとなるため、長期運用の複利効果がより効率的に働きます。
・強制的に積立を促すことができる
原則として60歳以降に一括または年金形式で受け取る仕組みで、老後に向けた強制的な積み立てを促してくれる制度でもあります。
2-3-2.iDeCoのデメリット
・原則60歳まで引き出せない
一度拠出したお金は原則として途中で引き出すことができず、急な出費やライフイベントへの対応が難しいという点が大きな注意点です。
・商品選定と資産配分を自分で管理する必要あり
投資信託や定期預金などから自分で運用商品を選び、定期的に見直す必要があるため、ほったらかしでは適切なパフォーマンスが得られないことも。
・所得が少ない人には節税メリットが薄い
所得控除という性質上、非課税世帯や課税所得が少ない人は、節税効果をあまり実感できないという側面もあります。
iDeCoや企業型DCは、「長期」「計画的」「税制優遇」という3つの要素を重視した資産形成手段として活用価値の高い制度です。ただし、その性質上、一度拠出すると「原則60歳まで使えないお金」になるため、他の資産とのバランスや流動性の確保も意識しながら設計することが重要です。
2-4.債券投資(国債・社債)
資産運用というと、株式や不動産のような「増やす」イメージが先行しがちですが、もう一つの重要な軸が「守る」資産を持つことです。その代表格が、国債や社債といった債券投資です。
債券はあらかじめ定められた利率で運用され、満期まで保有すれば元本と利息が返ってくる仕組みです。その性質から、リスクを抑えながら安定的に運用したい人に選ばれています。
ここでは、そんな債券投資のメリットと注意点を見ていきましょう。
2-4-1.債券投資のメリット
・元本の安全性が比較的高い(特に国債)
国債であれば国が発行体となるため、信用力が高く、デフォルトの可能性が極めて低いので、リスクを抑えたい人には適した選択肢です。
・利回りが安定している
株式のような価格変動は少なく、決まったタイミングで安定的に利息を受け取れることが、安心感につながります。
・ポートフォリオの安定装置として機能する
債券は株式や不動産とは異なる値動きをするため、全体のバランスを取るための“土台*として重要な役割を果たします。
2-4-2.債券投資のデメリット
・リターンは相対的に低い
安定している分、得られる利息は株式や不動産などに比べて控えめになります。特に金利が低い時期には、インフレに実質利回りが負けてしまうこともあります。
・金利上昇局面では価格が下落する
債券価格は金利と反比例の関係にあり、将来的に金利が上昇すると、保有している債券の価値が下がるリスクがあります。
・長期債の場合、途中解約で損をするリスクあり
満期まで保有すれば元本は返ってきますが、途中で売却する場合は市場価格によって損失が発生する可能性があります。資金拘束期間をよく考えて購入することが大切です。
債券投資は、資産全体のボラティリティ(値動きの激しさ)を抑えるクッション材として優れた存在です。ただし、金利や満期、流動性といった点も考慮しながら、ほかの資産とバランスを取りつつ取り入れることが重要です。
2-5.金(ゴールド)
古来より価値の保存手段として重宝されてきた金は、現代でも有事の備えやインフレ対策として、資産の一部に取り入れる投資家が増えています。
また、金以外にも原油、小麦、プラチナなどの商品(コモディティ)に分散投資できるETFなども登場し、金融資産とは異なるリスク分散の受け皿として注目されています。
「金(ゴールド)」は、トランプ政権に端を発した関税政策の影響により、多くの投資家が安全資産である金へと向かい、2025年4月に最高値を更新しています。
2-5-1.金投資のメリット
・インフレや有事に強く、実物資産としての価値あり
通貨の価値が下がる局面でも、金の価値は相対的に保たれやすいとされています。戦争や経済危機といった非常時に「安全資産」として資金が流れ込む傾向があります。
・通貨や株式と異なる値動きで分散効果がある
金は株や債券と連動しにくいため、ポートフォリオに組み込むことで全体の値動きをマイルドにする効果が期待されます。
・長期保有で価値を維持しやすい
短期的なリターンは期待しにくい一方で、「価値の保存手段」としては長い歴史があり、安定感がある資産クラスといえます。
2-5-2.金投資のデメリット
・配当や利息がなく、収益は値上がり頼り
株や債券と違って、金は保有していても収入を生まないため、キャッシュフローが必要な人には向きません。
・保管コスト・盗難リスクなどがある(現物)
実物の金を保有する場合は、金庫の用意や保険加入が必要になることもあり、見えにくいコストがかかる可能性があります。
・価格が高騰しているタイミングでは割高リスクも
金は「人気が集まる=価格が上がる」資産であるため、一時的な過熱感のある局面では高値づかみのリスクも伴います。
2-6.暗号資産(ビットコイン等)
ここ数年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)が大きな注目を集めてきました。株式や債券といった従来の金融資産とは一線を画す、新しい投資対象として台頭しており、若年層を中心に保有者が急増しています。
その一方で、暗号資産は価格の変動が極端に大きく、規制や技術面での不安も残る投資対象であり、扱いには慎重さが求められます。暗号資産の特徴とそのメリット・デメリットを整理します。
2-6-1.暗号資産のメリット
・ハイリターンを狙える
暗号資産の代表格であるビットコインは、数年で数倍以上に価格が跳ね上がった実績もあり、短期的に大きなリターンを得られる可能性を秘めています。2010年代末にはビットコインブームが起き、「億り人」も話題となりました。
・24時間取引が可能
通常の株式市場と異なり、土日・深夜を含めていつでも取引ができるため、ライフスタイルに合わせた運用がしやすいという利点があります。
・ブロックチェーン技術の進化による暗号資産の需要拡大
暗号資産の根幹技術であるブロックチェーンは、分散型台帳として金融や物流、行政などさまざまな分野での応用が進んでいます。この技術の社会的信頼性が高まることで、暗号資産そのものの需要や価値が将来的に伸びると期待されています。
2-6-2.暗号資産のデメリット
・価格変動が極端で投機性が高い
ビットコインは数時間で10%以上の値動きをすることも珍しくなく、投資というより“投機”に近い側面が強いのが現状で、冷静な判断力が求められます。
・法制度が整備されておらず、リスクが不透明
国によって暗号資産に対する規制が大きく異なり、税制や取扱ルールも流動的です。将来的な禁止・制限リスクもゼロではありません。
・セキュリティリスクや取引所破綻の懸念
これまでにハッキングや取引所破綻による資産喪失の事例もあり、ウォレット管理や取引所選定には十分な注意が必要です。
暗号資産は、資産運用の中でリターンを高める“スパイス”的な位置づけとして捉えるのが現実的です。ポートフォリオ全体の中でも、資産の一部(5%以内など)に限定して持つというのが一般的な戦略です。魅力とリスクを正しく理解したうえで、冷静な姿勢で向き合うことが求められます。
2-7.外貨預金・FX
国内にいながら海外通貨に投資する方法として、外貨預金やFX(外国為替証拠金取引)を活用する人も増えています。円だけで資産を保有することに不安を感じる人にとって、通貨分散は有効な資産防衛策の一つといえるでしょう。
一方で、為替は株式以上に読みづらく、思わぬ損失につながる可能性もある投資領域です。
ここでは、外貨資産に投資する際のメリットとデメリットを整理します。
2-7-1.外貨資産のメリット
・為替差益や金利差益が狙える
外貨預金では、円安になれば為替差益が得られるほか、外貨建ての預金金利が日本より高い場合、利息収入も期待できます。FXでも金利差に基づいたスワップポイント(利息)の受け取りが可能です。
・分散投資の一環として通貨リスクを分けられる
円だけで資産を保有するリスク(円安・インフレ)に備える意味で、複数通貨に分けて持つことはリスク管理として有効です。
・高金利通貨を選べば金利収入も得やすい
トルコリラやメキシコペソ、南アフリカランドなどの高金利通貨を対象にすれば、金利収入を目的とした投資も可能です(ただしハイリスク)。
2-7-2.外貨資産のデメリット
・為替リスクが大きく元本割れも
為替レートの変動によって、たとえ外貨建てで元本が保証されていても、円に換算した時に損失となるリスクがあります。
・手数料やスプレッドがかかる
外貨預金では為替手数料が、FXではスプレッド(売値と買値の差)が発生し、実質的なコストとしてパフォーマンスに影響を与えることがあります。
・FXは特にレバレッジによる損失リスクが大
少額で大きな取引ができるFXは、短期で利益を狙える反面、損失も一瞬で膨らむリスクがあるため、初心者には慎重な運用が求められます。
外貨資産は、資産の一部を通貨分散する目的で取り入れると効果的です。
特に外貨預金は比較的安定的に保有できる一方、FXは短期勝負・上級者向けという位置づけで考えておくと良いでしょう。
3.不動産投資のメリットとデメリット
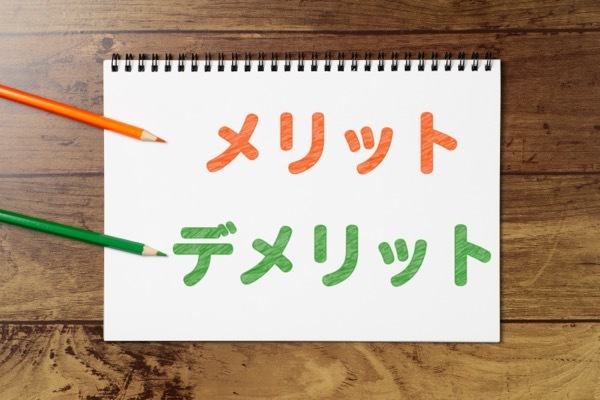
株式や投資信託といった金融資産とは異なり、「実物資産」である不動産への投資は、一定の安定性や資産防衛力を備えているとして、再び注目を集めています。特に、長期的なインフレや相場の変動が読みにくい時代においては、相関の低い資産としてポートフォリオに加える価値があると考える投資家も少なくありません。
一方で、不動産投資には初期コストや管理上のハードルといった独特のリスクや手間も存在します。ここでは、その特徴をメリット・デメリットの両面から整理していきましょう。
3-1.不動産投資の6つのメリット
まず不動産投資の代表的な6つのメリットを説明します。
・家賃収入による安定したインカムゲイン
毎月の賃料として得られる家賃収入は、株式の配当や債券の利息に近い“安定収入”となり、長期で安定的なキャッシュフローを見込めます。
・景気に左右されにくく、長期的な収益が見込める
地価や賃料は短期的には変動しても、人口や地域特性に支えられたエリアであれば、比較的安定的な運用が期待できます。
・株や仮想通貨と相関が低く、分散投資効果が高い
株式市場が下落しても、不動産価格や家賃が必ずしも連動するとは限りません。異なる値動きをする資産として、ポートフォリオのリスク低減に役立ちます。
・実物資産ゆえのインフレ耐性がある
インフレによって物価や建築コストが上がると、不動産価値や家賃も相対的に上昇しやすく、物価の変動に対するヘッジ手段となり得ます。
・ローン活用によりレバレッジが効く
金融機関からの借入を使うことで、自己資金よりも大きな資産運用が可能になります。これにより、手持ち資金の少ない人でも参入できる余地が生まれます。
・節税、相続対策としての機能も
減価償却費による所得圧縮や、小規模宅地の特例などを活用すれば、節税・相続対策としても一定の効果が期待できます。資産家が不動産を好む理由の一つです。
3-2.不動産投資のデメリット
つづいて4つのデメリットを説明します。
・初期費用が大きく、借入リスクがある
不動産の購入には数百万〜数千万円の資金が必要で、物件取得費・諸費用・ローン審査といったハードルも存在します。金利上昇局面では返済額が増えるリスクもあります。
・空室や家賃下落リスクがある
入居者が見つからなければ家賃収入はゼロです。エリアや物件選定を誤ると、収支が赤字化するリスクもあります。周辺環境の調査は必須です。
・管理や修繕に手間がかかる
建物の劣化や設備不良への対応、入居者トラブルなど、物件オーナーとしての対応業務が発生します。管理会社に委託する場合も、その質が問われます。
・流動性が低い(現金化しづらい)
株のようにすぐ売却できるわけではなく、物件の売却には時間もコストもかかります。緊急時の資金調達手段としては向いていません。
不動産投資は、資産形成の「柱」の一つとして長期視点で取り組む価値のある投資です。
ただし、「必ず儲かる」ものではなく、リスクや手間も含めたうえで、自分のライフプランや資産全体のバランスに合うかを見極めることが大切です。
4.制度に頼るだけでなく、自分の判断軸を持とう

NISAやiDeCoといった非課税制度は、資産形成を後押しする有効な仕組みです。しかし、世界経済の不確実性が高まる今、制度だけに頼るのではなく、複数の投資手段を自分なりに組み合わせていく視点が求められています。
本記事で紹介した投資信託、株式、債券、金、不動産、暗号資産など、それぞれの資産にはリターンとリスク、適した役割があります。大切なのは、どれか一つに正解を求めるのではなく、自分の資産状況や将来設計に合ったバランスを考えることです。
特に不動産は、インカムと資産保全の両面に強みがある「堅実な柱」として再評価されています。もし興味を感じたなら、まずは無料相談や少額シミュレーションなど、できる範囲から情報収集を始めてみるのも良いでしょう。
これからの資産形成は、「制度の活用」と「自分の判断軸」、その両方を持つことで、はじめて安定感のある選択へと近づいていきます。
>>【無料eBook】30代で知りたかった「お金」の極意 後悔しない8つのポイント
【オススメ記事】
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・独身男性の老後の生活費は?「一生ひとり」ならお金の準備はお早めに!
・時には遊び心も!テーマ型投資について
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・お金はありすぎてもダメ!?「限界効用の逓減」に見る幸せな億万長者の条件

