

分散投資は、投資の基本として広く知られています。そのメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。本記事では、ポートフォリオの組み方を交えながら分散投資の特徴を解説します。また、不動産投資で分散投資を行う際の注意点についても紹介します。
目次
1.分散投資とは?

分散投資とは、投資する商品のカテゴリーや購入時期を分散させてリスクを減らす投資手法です。「すべての卵を1つのカゴに盛るな」という投資格言があります。1つのカゴ(資産)にすべての卵(お金)を盛って(投じて)しまうと、落とした(暴落した、破綻した)ときにすべて割れて(失って)しまいます。しかし、いくつかのカゴに分けて卵を盛れば、1つ落としてもほかの卵は割れずに済むという格言です。
このいくつかのカゴに分けて盛るという考え方が分散投資の基本となります。代表的な分散投資の方法として以下の3つが挙げられます。
1-1.地域の分散
世界各地では常に戦争や紛争、災害、経済危機などが起きています。中国が不況に陥るなど、大国だからといって安全なわけではありません。中国経済が絶好調だったときに中国株に集中投資した人は、現在はかなり含み損になっている可能性もあります。同じように米国株が史上最高値を更新して絶好調であっても、外国株に投資するときは地域を分散したほうが無難です。
また不動産投資では、すべての物件を同じ地域に保有すると、大きな災害が起きたときにまとまって被害を受ける可能性があります。複数物件を保有する場合は、東京、横浜、名古屋など賃貸需要の多い都市の中で分散投資をすることが望ましいです。
ただし、億ションなど高額な不動産を購入するとポートフォリオで不動産だけが突出してしまうため、ワンルームマンションで分散投資することがバランス面では適しています。
1-2.資産の分散
資産カテゴリーも分散する必要があります。資産カテゴリーとは、株式、債券、不動産など商品別の区分のことです。そこから株式なら個別銘柄、債券なら国内債券と外国債券、不動産ならマンション、アパート、オフィスなどさらに細分化されます。
投資商品にはローリスク・ローリターンのものと、ハイリスク・ハイリターンのもの、あるいはその中間のものがあります。債券や預貯金のようなローリスク・ローリターンの商品だけでポートフォリオを組んでしまうと、資産の成長が見込めません。
一方でハイリスク・ハイリターンの商品が多いと、大きなリターンが期待できる半面、資産を減らすリスクも高くなります。
ポートフォリオを組む場合は、安定と成長のバランスが取れた商品構成にする必要があります。
1-3.時間の分散
金融市場は常に動いているので、1つの時期に集中して資金を投じるのはリスクが高いです。リーマンショックの直前に集中投資していたらかなりの損失を被ったことでしょう。このような金融危機や大きな災害、戦争などの影響は長期分散投資することでかなり抑えることができます。
特に「積立投資信託」は時間の分散に最適です。毎月給与の中から決まった金額を決まった日に銀行自動引き落としで購入していけば、相場が高い月は少ない口数を、安い月は多くの口数を購入することになるので、長期では買値が平準化します。定期的に購入していくので、個別株のように高値掴みする心配がありません。投資の世界では有名な「ドルコスト平均法」を応用した投資方法です。
2.分散投資のメリット

分散投資するメリットとして、以下のような点が挙げられます。
2-1.リスクを軽減しやすい
分散投資の最大のメリットはリスクを軽減しやすいことです。最大のリスクは「価格変動リスク」ですが、ほかにも企業や国家が破綻する「信用リスク」、希望する価格で売れない「流動性リスク」、通貨の価値が変動する「為替変動リスク」、地域紛争や経済危機が発生する「カントリーリスク」などがあります。
日本国債以外は何らかのリスクは付きものなので、分散投資でリスクを軽減することが資産を減らさないための最適な対策です。
2-2.安定した投資効果が期待できる
分散投資は安定した投資効果が期待できるのもメリットの1つです。どのような投資商品であれ、一方的に価格が上がり続けることもなければ、下がり続けることもありません。分散投資していれば、下がっているものもあれば、上がっているものもあるという状態になります。
例えば、2020年に起きた新型コロナウィルスの感染拡大で株式市場が大きな暴落に見舞われたときも、安定資産である債券や金、不動産はほとんど影響を受けませんでした。このとき、株式、債券、金、不動産に分散投資していた人は、株式を慌てて売ることなく、その後のリバウンド相場を待つことができたでしょう。
分散投資こそ安定した投資効果を得る秘訣といえます。
3.分散投資のデメリット
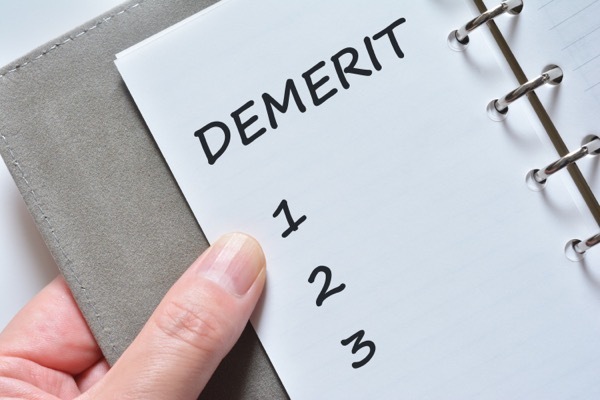
安定した資産運用に必要な分散投資ですが、以下のようなデメリットもあります。
3-1.短期間で高いリターンを得にくい
分散投資は資金も分散されるので、短期間で高いリターンを得ることは難しいです。1つの銘柄に1,000株集中投資すると、100円株価が上がれば10万円の利益が出ます。しかし、100株ずつ10銘柄に分散した場合は、1つの銘柄が100円高になっても1万円の利益にしかなりません。10万円の利益が出るまでには集中投資の場合より時間がかかります。
3-2.投資先の管理が必要
1つの銘柄を大量に保有するのであれば状況を把握するのは簡単ですが、分散投資で銘柄数や資産カテゴリーが多くなれば管理が必要になります。
基本的に分散投資で長期間運用すれば、配当金や家賃収入などのインカムゲインが積み重なっていくので、資産残高は増えていくのが普通です。配当金でまた別の銘柄を購入するケースもあるので、エクセルで資産一覧を作成して、毎月末などに時価総額を確認することが有効です。利回り5%を目標にする場合、どの程度目標と乖離しているかも確認することができます。
4.分散投資とポートフォリオ

分散投資を行う場合に欠かせないのがポートフォリオの作成です。ポートフォリオは安定した運用をするための設計図のようなものです。ポートフォリオがないと行き当たりばったりの野放図な資産運用になる恐れがあります。
4-1.ポートフォリオの組み方
ポートフォリオを組む際は、より分散効果が高い商品で構成することが大事です。具体的には「商品をばらけさせる」「年齢に合わせた計画を立てる」の2つの考え方に基づいて組んでいきます。
4-1-1.商品を分散させるポートフォリオ
投資する資産カテゴリーや銘柄、業種などで分散する方法です。2つのパターンに分けて見てみましょう。
A.最も基本的な分散
| 国内債券 25% | 外国債券 25% | 国内株式 25% | 外国株式 25% |
国内最大の機関投資家であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が組んでいるポートフォリオは、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式を25%ずつ保有するというものです。これがポートフォリオの基本形と考えてよいでしょう。債券と株式で「商品の分散」、国内と外国で「地域の分散」、ローリスクとハイリスクで「リスクの分散」が図られています。
B.業種による分散
| 小売株 25% | 通信株 25% | 自動車株 25% | 電機株 25% |
株式を組み入れる際は1つの業種に偏らず、内需関連株と輸出関連株に業種を分けて保有することで、円安または円高の為替変動があったときにリスクを減らすことができます。自動車や電機などは円安になると買われ、円高になると売られる傾向があります。半分ずつバランス良く保有することで、値下がりリスクを軽減できます。
4-1-2.年齢に合わせたポートフォリオ
投資する年代によっても組むべきポートフォリオは異なります。ライフステージに合わせた年代別のポートフォリオを見てみましょう。ここではローリスクの債券、ミドルリスクのREIT、ハイリスクの株式で構成するものとします。
A.20代のポートフォリオ
| 株式 60% | REIT 20% | 債券 20% |
20代はまだ独身のケースが多いので、株式を中心として積極的に資産の増加を狙うのもよいでしょう。若い年代であれば多少の損失を被っても、先が長いので挽回することは十分に可能です。ただし、株式も優良株に絞ればそれほどリスクが高いわけではありません。
B.30代のポートフォリオ
| 株式 50% | REIT 25% | 債券 25% |
30代は多くの場合、結婚して子どもも産まれる年代なので、出費も増えます。株式で積極的に運用しつつ、半分はREIT・債券で安定した分配金や利息を得るほうが適しているでしょう。年齢や家族構成を考えると、損失を挽回できるのは30代までと考える必要があります。
C.40代のポートフォリオ
| 株式 40% | REIT 30% | 債券 30% |
40代は子どもが大学に進学する年代なので、最も多くお金がかかる時期といわれています。株式で損失を出すことは避けなければならないので、半分以上をREITと債券で運用したほうが無難です。
D.50代のポートフォリオ
| 株式 30% | REIT 30% | 債券 40% |
50代になると定年を意識した資産運用が必要です。株式で大きな利益を狙うよりも、債券の比率を高めて安定性の高いポートフォリオにすることが望ましいです。すでに教育費はかからなくなっているので、金利の高い10年長期国債で運用するのもよいでしょう。
E.60代のポートフォリオ
| 株式 20% | REIT 30% | 債券 50% |
60代は会社を定年退職して、一般的には65歳から年金生活に入ります。現役時代より月収は減るので、公的年金に加えて株式の配当金、REITの分配金、債券の利息で老後生活を送ることになります。値下がりリスクは極力抑えなければなりません。キャピタルゲイン(売却益)よりインカムゲイン(配当金などの定期収入)を目的にしたポートフォリオにする必要があります。
以上が年齢別に見たポートフォリオの一例ですが、このポートフォリオの「株式」の部分を「株式投資信託」にすることも可能です。投資信託なら個別株よりはリスクを軽減できます。
また各年代のリスク許容度によって、外国株式や外国債券を組み入れるのもよいでしょう。
4-1-3.不動産を組み入れたポートフォリオ
| 不動産 50% | 株式 25% | 債券 25% |
不動産は高額な商品なので、半分程度の比率にすることでポートフォリオのバランスを安定させることができます。例えば1億円の資産を運用する場合なら、新築ワンルームマンションに5,000万円、株式と債券に2,500万円ずつ投じれば、不動産の家賃収入を得つつ、株式の値上がり益も狙えます。
4-2.ポートフォリオは定期的な見直しが重要
ポートフォリオは一度組んだら終わりではありません。「リバランス」と呼ばれる定期的な見直しが必要です。個人の場合は機関投資家と違って事業で投資するわけではないので、ライフステージに合わせて目標を立てることが必要になります。
老後資金2,000万円不足問題に備えて、65歳までに2,000万円の資産を築くことを目指すのは典型的な目標例です。
例えば、25歳から65歳までの40年間で2,000万円を目指すなら、年間で50万円ずつ増やしていく必要があります。安全を期して債券を多くしたために45万円ペースでしか増えないという場合は、リバランスを行い、高配当株などを増やして配当収入を多くするなどの工夫が必要です。
4-3.ポートフォリオに不動産を組み込むメリット
ポートフォリオに不動産を組み込むことも安定した運用につながります。不動産は金融投資に比べて価格変動が緩やかです。建物は経年劣化により徐々に価値が下がるものの、減価償却を通じて会計上の利益を調整することで、実質的なキャッシュフローを増やすことが可能です。
家賃収入は借り入れがある場合ローンの支払いに充てられますが、完済後は物件が純資産となります。不動産は預貯金、株式と合わせて「資産三分法」の一角を占める資産としても推奨されている商品です。
この3つの資産を持つことによって、ローリスク・ローリターン(預貯金)、ミドルリスク・ミドルリターン(不動産)、ハイリスク・ハイリターン(株式)とバランス良くリスク分散することができます。
5.不動産投資で分散投資する際の注意点

不動産投資で分散投資を行う際は、保有エリアや購入時期に注意が必要です。エリアによるリスク分散や市場の動向を踏まえたタイミングを見極めることが、安定した運用の鍵となります。
5-1.物件を保有するエリア
物件を保有するエリアは分散したほうが安全です。保有するエリアに関しては、需要面と災害リスクの観点から考える必要があります。
不動産投資を行う場合、「東京23区駅徒歩10分以内」という好立地物件を買いたくなるのが普通です。しかし、東京23区は物件価格が高いので、名古屋や横浜などほかの人気エリアに物件を持つことも検討する必要があります。
特に横浜はSUUMOが発表している「住みたい街ランキング」で毎年1位に選ばれる人気エリアなので、東京23区に負けない投資効果が期待できます。
このように東京23区以外にも、需要が期待できるうえに物件価格が割安なエリアは存在します。一極集中を避けることで、リスクを抑えた投資が可能です。
さらに、日本は地震大国であり、災害リスクへの注意も欠かせません。近年は数年おきに大規模な地震が発生しており、いつどこで起きてもおかしくない状況です。それに加え、毎年のように豪雨災害も発生しています。一つのエリアに物件を集中させると、管理の効率は良くなりますが、災害が起きた際にはすべての物件が同時に被害を受けるリスクがあります。
しかし、全国各地に物件を分散して保有することで、災害が発生しても被害を最小限に抑えることが可能です。地震や豪雨が日本全国で同時に起こることはないため、エリア分散はリスク管理において非常に有効な手段といえます。
5-2.物件の購入時期
同じ時期に複数の物件を購入するのは避けるべきです。購入時期を分けたほうが良い理由は主に2つあります。
1つはローン金利に関する問題です。金利は変動するため、複数の物件で同じタイミングでローンを組むと、金利が上昇した際に全てのローンに一斉に影響が及び、負担が増えるリスクがあります。金利上昇局面では無理に両方買わずに、金利が下落見通しとなったらもう1件を買うようにすれば、金利変動の影響を抑えることができます。
もう1つが修繕費の問題です。同じような築年数の物件を2つ買った場合、修繕や設備の交換が同じタイミングで発生する可能性があります。修繕費の発生が集中しないためにも時期を分けて購入するほうが効率は良いといえます。
6.分散投資の基本を押さえ、最適なポートフォリオを構築しよう

分散投資が投資の基本であることを確認しました。少なくとも分散投資を心がければ、大きく資産を減らすことはないでしょう。そのためにもポートフォリオを作成して、行き当たりばったりではない安定した運用を行うことが大切です。
ただし、分散投資であっても短気売買が中心であれば、すぐに構成が変動してしまうので、ポートフォリオを組む意味はあまりないでしょう。分散投資は長期投資で行ってこそ効果を発揮します。
不動産投資は長期で家賃収入を得ていく安定した商品なので、ポートフォリオの中心に据えると資産運用全体を下支えすることが期待できます。
※記事中のポートフォリオは一例であり、投資効果を保証するものではありません。
>>【無料eBook】30代で知りたかった「お金」の極意 後悔しない8つのポイント
【オススメ記事】
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・独身男性の老後の生活費は?「一生ひとり」ならお金の準備はお早めに!
・時には遊び心も!テーマ型投資について
・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは
・お金はありすぎてもダメ!?「限界効用の逓減」に見る幸せな億万長者の条件

