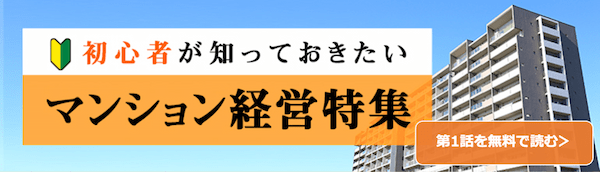「サラリーマンとして真面目に働くほど、給与から天引きされる税金の額にため息が出る…」
年収が上がるにつれて増えていく所得税や住民税の負担に、そう感じている方は少なくないでしょう。
その手取りを増やす有効な手段として「マンション投資による節税」が注目されていますが、「なんとなくお得」という曖昧な理解のまま始めると、思わぬ落とし穴にはまることも少なくありません。
この記事では、複雑な計算シミュレーションをあえて使わずに、節税の「本質的な仕組み」と「成功の勘所」、そして「絶対に知っておくべき注意点」を、誰にでも分かるように徹底解説します。
最後まで読めば、あなたが本当にマンション投資で節税メリットを享受できるのか、そしてそのためには明日からどう行動すべきかの道筋が見えてくるはずです。
目次
マンション投資の節税は「減価償却」を利用して赤字を作り、給与所得と相殺する仕組み
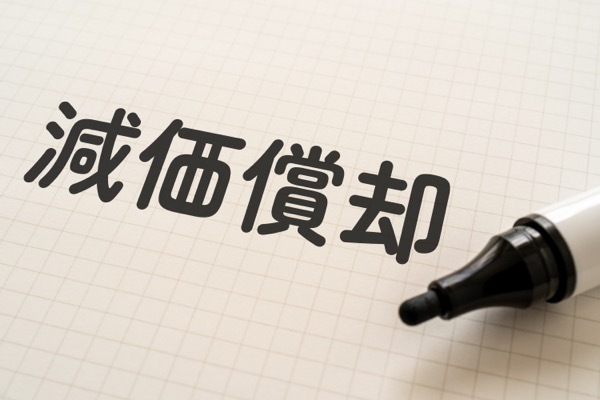
まず「マンション投資でなぜ節税できるのか?」。その仕組みは、以下の3ステップで成り立っています。
- 「減価償却費」という特別な経費を使って、不動産経営の帳簿上で赤字を作り出す
- その赤字を、あなたの給与所得(黒字)と「損益通算」する
- 課税対象となる所得全体を圧縮し、払いすぎた所得税・住民税の還付を受ける
これが、マンション投資による節税の肝です。ポイントは、実際には手元からお金が出ていっていない「減価償却費」を経費にできる点にあります。この魔法のような経費があるからこそ、「手元の現金はプラスなのに、帳簿上は赤字」という状況を作り出し、節税に繋げることができるのです。
マンション投資で節税ができる2つの重要キーワード

この仕組みを正しく理解するためには、どうしても避けて通れない2つの専門用語があります。
それが「減価償却(げんかしょうきゃく)」と「損益通算(そんえきつうさん)」です。
一見難しそうに聞こえますが、この2つさえ押さえれば、節税の全体像は驚くほどクリアになります。ここでは計算式は使わず、それぞれの「概念」を分かりやすく解説していきます。
① 減価償却:実際にお金は出ていかない「帳簿上の経費」
マンション投資における節税の最重要ポイントが、この「減価償却」です。
減価償却とは、「建物などの資産は、時間が経つにつれて価値が減少していく」という考え方に基づき、その価値の減少分を、数年~数十年にわたって経費として計上できるという会計上の仕組みです。
たとえば、新車を買っても、数年後には価値が下がっていますよね。それと同じ考え方です。
最大のポイントは、減価償却費が「実際には支出を伴わない経費」であるという点です。ローンの金利や管理費は実際にお金が出ていきますが、減価償却費は帳簿上にだけ存在する架空の経費。つまり、手元のキャッシュを減らすことなく、経費だけを増やすことができるのです。
この減価償却できる期間は、建物の構造によって法律で定められた「法定耐用年数」によって決まります。
- 木造:22年
- 鉄骨造(骨格材の厚さによる):19年~34年
- RC造(鉄筋コンクリート造):47年
RC造のマンションは耐用年数が長いため、長期間にわたって安定的に減価償却費を計上し、節税効果を持続させやすいという特徴があります。
② 損益通算:不動産の「赤字」と給与の「黒字」を合算する
サラリーマン・会社員がマンション投資で節税できる理由の核心が、この「損益通算」です。
損益通算とは、ある所得で生じた赤字を、他の種類の黒字の所得と合算できる制度のことです。会社員の場合、不動産所得で生じた赤字(主に減価償却費によって作られた赤字)を、給与所得の黒字と合算できます。
【損益通算のイメージ】
[給与所得 800万円] - [不動産所得の赤字 100万円] = [課税対象の所得 700万円]
このように、本来800万円に対してかかるはずだった税金が、700万円に対してかかる計算になるため、その差額分だけ所得税や住民税が安くなるのです。確定申告を行うことで、すでに給与から天引き(源泉徴収)された税金の一部が「払い過ぎ」だったと見なされ、手元に還付されます。
【不動産所得の計算で経費にできる主なもの】
- 減価償却費
- ローン金利(建物部分)
- 管理費、修繕積立金
- 固定資産税、都市計画税
- 損害保険料(火災保険・地震保険)
- 不動産会社への管理委託手数料
- 税理士費用など
一方で、ローンの元本返済額は経費にできないので注意が必要です。
【あなたはどっち?】節税効果が出やすい人・出にくい人の特徴

「なるほど、自分もマンション投資で節税したい!」と思ったかもしれませんが、少し待ってください。実は、この節税メリットは誰にでも同じように効果があるわけではありません。どのような人がメリットを享受しやすいのか、その「条件」と「原理」を理解することが重要です。
効果が出やすいのは「課税所得が高い」人
結論から言うと、マンション投資の節税効果は、年収(正確には課税所得)が高い人ほど大きくなります。
その理由は、日本の所得税が「累進課税」という仕組みを採用しているからです。これは、所得が高ければ高いほど、より高い税率が適用される制度です。
たとえば、同じ100万円の不動産赤字を損益通算した場合でも、
- 課税所得300万円の人(所得税率10%):約10万円の節税
- 課税所得1,000万円の人(所得税率33%):約33万円の節税 (※住民税率は一律10%のため、所得税と合わせると差はさらに広がります)
このように、適用される税率が違うため、還付される税金額に3倍以上の差が生まれるのです。このことから、節税効果はあなたの所得に大きく依存するという事実を理解しておく必要があります。一般的に、節税メリットを実感しやすいのは年収700万円以上が一つの目安とされています。
マンション投資節税で絶対に知るべき4つの注意点

マンション投資で成功するためにはデメリットや注意点を正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、特に重要な4つのポイントを解説します。
① 節税効果は永続しない(減価償却には期間の限りがある)
減価償却は、法定耐用年数に基づいて行われるため、いつまでも経費計上できるわけではありません。RC造マンションなら47年で償却期間が終わります。
減価償却費がなくなると、他の収支が同じでも経費だけが急激に減るため、帳簿上は黒字に転換します。これを「デッドクロス」と呼びます。デッドクロスを迎えると、キャッシュフローは変わらないのに納税額だけが増え、手残りが大幅に減少する可能性があります。そのため、減価償却期間が終わる前に売却するなどの出口戦略をあらかじめ考えておく、長期的な収支計画が重要になります。
② 税金の「繰り延べ」であり「免除」ではない
これは最も重要な注意点です。マンション投資による節税は、本質的には「税金の支払いを将来に繰り延べている(先送りしている)だけ」という側面があります。
なぜなら、物件を売却するときに、これまで減価償却費として経費計上してきた合計額は、物件の「取得費」から差し引かれるからです。取得費が下がると、その分「譲渡所得(売却益)」が大きくなり、売却時にかかる税金が増えるのです。つまり、運用期間中に節税した分を、売却時にまとめて支払うイメージに近いと言えます。
さらに、売却時の税率は物件の所有期間によって大きく異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率 約39%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):税率 約20%
最低でも5年以上は保有しないと、高い税率で課税されてしまい、せっかくの節税効果が吹き飛んでしまう可能性があるので注意が必要です。
③ 2020年税制改正による海外不動産への規制
2020年までは、海外の中古不動産(特にアメリカの木造物件など)を使い、建物の価値を短期間で大きく償却して巨額の赤字を作り出す節税スキームが一部で流行していました。
しかし、2020年の税制改正により、この海外不動産を利用した損益通算には厳しい制限がかけられ、現在ではこの手法を使うことはできなくなりました。このことからも、過度な節税テクニックに頼るのではなく、国内の優良な不動産に投資することが王道であることが分かります。
節税効果を最大化するマンション選びの3つのポイント

これらの注意点を理解した上で、節税メリットを享受しつつ、投資としても成功するためにはどのような物件を選べばよいのでしょうか。ここでは具体的な3つのポイントを解説します。
① 減価償却費の源泉「建物の価値割合」が高い物件
減価償却できるのは、不動産のうち「建物」部分だけであり、「土地」は減価償却できません。時間は経っても土地の価値は減らない、と考えられるからです。
したがって、物件価格に占める「建物の割合」が高い物件ほど、減価償却費を多く計上でき、節税効果も高まります。
売買契約書には土地と建物の価格が明記されているので、必ず確認しましょう。一般的に、地価が高い都心の物件は、土地の価格に引きずられて建物も高仕様・高層化する傾向があるため、結果として建物割合が高くなるケースが多く見られます。
② 長期で安定した経費計上が可能な「RC造」物件
前述の通り、建物の構造によって法定耐用年数は大きく異なります。
- 木造:22年
- 鉄骨造:34年
- RC造(鉄筋コンクリート造):47年
耐用年数が長いRC造のマンションは、木造アパートなどと比較して、長期間にわたって安定的に減価償却費を計上し続けられるという大きなメリットがあります。短期的な節税効果だけを狙うのではなく、長期的な資産形成を目指すサラリーマンにとって、堅実な選択と言えるでしょう。また、物理的な耐久性が高く、資産価値を維持しやすい点も魅力です。
③ 投資の大前提を満たす「安定した賃貸需要」がある物件
繰り返しますが、節税はあくまで副次的な効果です。大前提として、不動産投資そのものが成功すること(=空室にならず、安定した家賃収入を得られること)が最も重要です。
どんなに節税効果の高い物件でも、入居者がつかなければまったく意味がありません。その点で、人口が集中し、学生や社会人の単身者需要が常に旺-盛で家賃が下落しにくい都心のワンルームマンションは、長期的な資産形成と節税の両立を目指す上で、非常に合理的な投資対象と言えます。
まとめ 節税の仕組みを正しく理解して手取りを増やそう

マンション投資による節税の仕組みから注意点、そして具体的な物件選びのポイントまでを解説しました。最後に、全体の要点を振り返ります。
- マンション投資の節税は、「減価償却」で帳簿上の赤字を作り、「損益通算」で給与所得と合算して税金の還付を受ける仕組みである。
- 節税効果は「課税所得が高い人」ほど大きく、その本質は税金の「繰り延べ」であることや、減価償却期間に限りがあるなどの注意点も存在する。
- 節税効果を最大化し、投資としても成功するには、建物割合が高く、長期間安定して減価償却でき、かつ賃貸需要が旺盛な「都心のRC造ワンルームマンション」が有利である。
マンション投資における節税は、正しく理解し活用すれば、あなたの手取りを増やす強力な味方になります。しかし、それはあくまで安定した不動産経営という土台があってこそ輝くものです。まずはその本質的な仕組みをしっかりと理解することから始めてみてください。
>>【無料eBook】「借金は悪である」という既成概念が変わる本
【オススメ記事】
・副業で考える人生設計|マンション経営も視野に入れた副業の可能性
・首都圏でのマンション経営|覚えておくべき「相場感」を紹介
・始める前に読んでおきたい 初心者向け長期資産運用のコツがわかる本5冊
・土地とマンションの資産価値は?「売却価値」と「収益価値」
・人生はリスクだらけ……でもサラリーマンが行う対策は1つでいい