
不動産投資における事業形態は、大きく「個人事業主」と「法人」に分けることができます。最初は個人事業主として始めるケースが一般的ですが、所得が一定の水準を超えると、法人化したほうが節税効果が得やすいケースがあります。では、どのようなタイミングで法人化を検討すべきなのでしょうか。
本記事では、不動産投資で法人化するメリット・デメリットや法人化のタイミング、会社設立の流れなどについて解説します。
目次
1.不動産投資の法人化とは

不動産投資の法人化とは、個人で行っていた不動産事業を、会社を設立して法人として行うことを指します。個人事業主のときは、収益をすべて自分が受け取りますが、法人化すると、投資家が代表となる資産管理会社を設立し、会社を通じて事業を運営する形に変わります。
具体的には、個人が所有している不動産物件を、法人が金融機関からの借入金などで買い取って名義変更し、法人として不動産事業を行います。個人事業主と法人では課される税金の種類や税率、経費の扱い、損失の繰越期間などが異なります。以下に挙げるメリット・デメリットから、その違いを確認していきましょう。
2.不動産投資で法人化するメリット

不動産投資を法人化することで得られる主なメリットは、以下のとおりです。
2-1.実効税率の差で節税できる可能性がある
所得税と法人税の実効税率には違いがあります。所得税は累進課税で、所得が増えるにしたがって税率も上がります。これに対し、法人税は特定の法人を除いて税率が一律であるため、所得が一定の水準を超えると、法人化することで納税額が少なくなるケースがあります。
たとえば、個人の所得税は不動産所得とその他の所得を合算して最高45%まで課税されますが、法人税率は23.20%以上にはなりません。そのため、高所得になるほど両者の税負担の差は大きくなります。
2-2.経費計上できる範囲が広がる
個人事業主として不動産経営を行う場合、自宅を事務所として使う際には、家賃や光熱費などを「家事案分」し、どの程度を事業に使っているのかを明確にしたうえで経費計上する必要があります。個人では、計上できる経費に一定の制限があるのが実情です。
一方で法人化すると、事業に関連していれば、業務に関連する支出であれば広範囲にわたって経費として認められやすくなります。たとえば、自分自身の給与や、家族を社員にした場合の給与、役員報酬、退職金なども経費にできます。個人事業主では認められない項目です。
さらに、法人が不動産を売却して損失が出た場合、その損失を損金として処理し、他の収支と合算できる点も大きなメリットです。
2-3.赤字(欠損金)を10年間繰り越せる
個人事業主・法人ともに、青色申告を行っていれば、赤字を次年度以降に繰り越すことができます。個人の場合は最大3年間の繰り越しが可能ですが、法人では10年間に延長されます。(令和3年4月以降開始事業年度に適用)。
赤字を繰り越せる期間が長ければ、将来的に黒字になった場合に、その赤字と相殺することで課税所得を圧縮できます。修繕費や空室リスクなどで収益が不安定になりやすい不動産経営においては、10年間の繰り越しが認められるのは大きな利点です。
2-4.相続税対策ができる
個人で多くの不動産を所有していると、家賃収入が積み重なることで相続財産が増え、多額の相続税が発生する恐れがあります。このようなケースでは、相続税対策として法人化する人もいます。会社を設立して不動産の所有権を法人に移せば、家賃収入が法人の所得となり、個人の相続財産を減らすことにつながります。
さらに、家族を役員として登用し役員報酬を支払えば、相続財産の一部をあらかじめ渡しているのと同様の効果が得られます。ただし、役員報酬は給与所得として課税対象となるため注意が必要です。また、会社の後継者を誰にするかといった、事業承継の問題についても事前に考慮する必要があります。
2-5.所得を分散できる
所得は多ければ多いほど良いと思いがちですが、所得を分散させたほうが有利な場合もあります。
前項の相続税対策とも一部重なる内容ですが、法人化すると、家族を社員として雇用し、給与を支払うことが可能になります。さらに、個人と法人で所得を分散させることにより、いずれか一方に過度な税負担がかかることを避けられます。結果的に、全体としての税負担を抑えることが可能になります。
3.不動産投資で法人化するデメリット
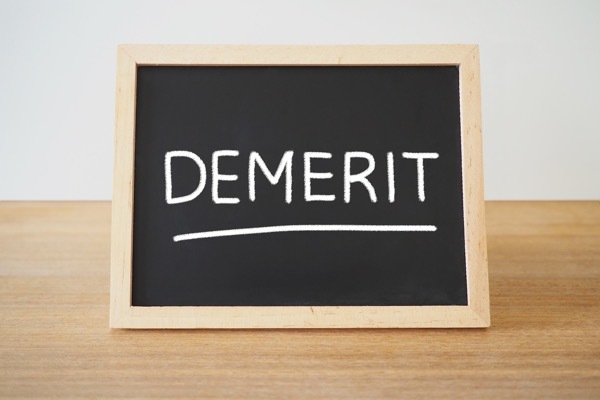
不動産投資の法人化には有利な面が多くありますが、一方で見落とせないデメリットも存在します。法人化によって生じるマイナス面も踏まえたうえで、慎重に判断することが重要です。
3-1.コストと手間が増える
法人化には、コストと手間がかかります。個人事業主であれば開業費用はかかりませんが、会社を設立する際には、株式会社なら20~30万円程度、合同会社であれば6~10万円程度の設立費用がかかるといわれています。
また、個人事業主のうちは自身で経理や確定申告を行う人も多くいますが、法人化して事業が拡大していくにつれ、経理や申告業務の手間が増え、税理士に依頼するケースも多くなります。その際は税理士報酬が発生します。さらに、法人化は社会保険への加入が義務付けられており、従業員の社会保険料の半分を事業者が負担しなければならない点もデメリットです。
法人化により得られるメリットと、こうしたコストや事務負担のデメリットをよく比較したうえで、メリットが上回ると判断できる場合にのみ、法人化を検討するべきでしょう。
3-2.赤字でも税負担がある
法人は赤字でも最低限の税金支払いが発生します。個人事業主が不動産専業で赤字になれば、所得水準によって住民税の支払いが免除される可能性があります。ところが、法人の場合は赤字だった場合も、従業員数と資本金から算出される住民税の均等割だけは支払う義務があります。
法人住民税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内です。3月31日が終了日の場合、納付期限は5月31日となります。
また、消費税も預かった仮受消費税が支払った仮払消費税より多い場合は申告と納税が必要です。消費税は赤字の場合でも法人としての税的な負担は免れません。
3-3.長期保有物件売却時の税率優遇がない
不動産を売却したときの譲渡所得税には「短期譲渡所得税」と「長期譲渡所得税」の2種類があります。税率は短期譲渡所得税(5年以下保有)が39.63%に対し、長期譲渡所得税(5年超保有)は20.315%と倍近い開きがあります。個人事業主であれば5年超保有することで低い税率が適用されます。
一方、法人にはこのような長期保有による税率の優遇措置がありません。普通法人の場合、課税所得800万円以下の部分には15%、800万円超の部分には23.20%の法人税が課されます。
4.不動産投資で法人化するタイミングや目安
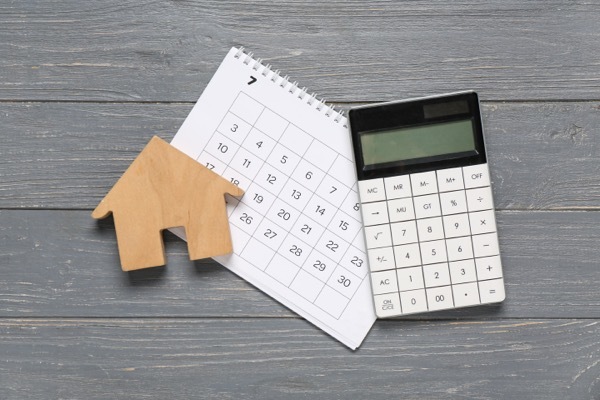
個人事業主として始めた不動産投資を、どのタイミングで法人化すべきかを考える際には、次の3つの目安が参考になります。
4-1.黒字運営で課税所得が900万円を超えた場合
| 所得税率 | 法人税率(普通法人の場合) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 課税される所得金額 | 税率 | 課税される所得金額 | 税率 | ||
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 適用除外事業者 | 19% | ||
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | ||||
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 年800万円超の部分 | 23.20% | ||
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 上記以外の普通法人 | 23.20% | ||
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | ||||
| 40,000,000円以上 | 45% | ||||
マンション経営などで黒字運営が続き、課税所得が900万円を超えると、所得税率はそれまでの23%から33%へ一気に上がります。一方、法人税率は原則として23.20%であるため、この水準を超えると法人化したほうが納税額を抑えられる可能性が出てきます。
課税所得が899万9,000円までは、所得税の最高税率が23%で、法人税率よりも低い水準にとどまります。しかし、900万円を超えると所得税率が33%に上がるため、法人化による節税効果が期待できるようになります。そのため、課税所得が900万円を超えるかどうかが、法人化を検討する際の一つの目安になるといえるでしょう。
4-2.不動産投資を今後拡大したい場合
将来的に複数の物件を保有したい、あるいは事業として本格的に拡大したいと考えている場合も、法人化を検討するタイミングといえます。
例えば、課税所得が4,000万円を超えると、所得税の最高税率である45%が適用されます。これは法人税率(23.20%)の約2倍にあたるため、高収益が見込まれる場合には、早めに法人化を検討することで、税負担を抑えることが可能になります。
また、法人であれば金融機関からの融資が受けやすくなるケースもあり、事業拡大にとっては有利な側面もあります。今後の投資計画に応じて、早めに法人化を視野に入れることで、長期的な税務・資金繰りの安定につながります。
4-3.専業で不動産所得330万円以下の場合は必要なし
不動産投資を専業で行っており、所得が330万円以下である場合は、所得税率が5~10%にとどまるため、法人税率(15%:年間所得800万円以下の部分)よりも低くなります。そのため、法人化による節税効果はほとんど期待できません。
さらに、法人化には司法書士報酬や法人住民税など、設立および運営にかかるコストや手間も発生します。これらを総合的に考えると、所得が330万円以下の段階では、法人化するメリットはあまりないといえるでしょう。
所得が330万円から899万9,000円の場合、所得税率は20~23%となり法人税率(15%)を上回りますが、法人化にともなう費用や負担を考慮すると節税効果は限定的です。やはり、前述のとおり、所得が900万円を超えてから法人化を検討するのが現実的といえるでしょう。
5.不動産投資で法人化するときの流れ

個人事業主として不動産投資を行ってきた人が法人化を検討する際、「どのような手続きが必要なのか」と不安に感じることもあるでしょう。法人設立にはいくつかのステップが必要ですが、流れを把握しておけば、準備もスムーズに進められます。
ここでは、不動産投資における法人化の一般的な手続きの流れを紹介します。
5-1.会社設立の準備
まずは、会社設立にあたって法人形態を決める必要があります。一般的には株式会社を選ぶケースが多いですが、合同会社、合資会社、合名会社などの選択肢もあります。これらは総称して「持分会社」と呼ばれます。各会社形態の概要は以下のとおりです。
出資者が経営者となり、出資した社員すべてに会社の意思決定権があります。組織の構成や利益配分を自由に設計でき、柔軟性の高い経営が可能です。全員が有限責任社員であり、出資額以上の責任を負うことはありません。
・合資会社
事業を行う無限責任社員と、出資のみを行う有限責任社員とで構成されます。経営破綻した場合、無限責任社員が全責任を負うため、現在はあまり見られない形態です。
・合名会社
出資者全員が無限責任社員となる会社形態です。各社員が業務執行権と代表権を持つため、複数の個人事業主が集まって運営するスタイルに近い形です。会社が債務超過に陥った場合は、全社員が連帯して返済義務を負います。
会社形態を決めたら、次に会社の概要を定めます(以下は株式会社の例です)。
・本店(本社)所在地
・資本金
・発起人(出資者)
・各発起人の出資額
・取締役(株式会社の場合は1名以上置くことが必要)
・会社設立の目的
会社概要が決まったら、法人の設立に必要な代表印、銀行印、社印を用意します。印鑑の役割は以下のとおりです。
契約書への押印や会社設立の登記申請書に捺印するときに使います。大きさは1辺の長さが「1センチ超で3センチ以内の正方形に収まる印鑑」と定められています。
・銀行印
銀行口座を開設するときに使います。
・社印
主に領収書や請求書に押印するときに使います。
5-2.定款作成と認証
次に、会社を運営するうえでの基本的なルールを定めた「定款」を作成します。定款は会社法に基づいて作成し、法人設立に必要な事項を明記する必要があります。定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」は以下のとおりです。
・商号
・本店(本社)所在地
・設立に際して出資される財産の価額又は最低額
・発起人(会社設立の責任者)の氏名又は名称及び住所
定款が完成したら、「定款認証」を受けます。これは公証役場において、公証人が定款の内容を確認し、正式な手続きを経て認証を行うものです。株式会社の設立にはこの手続きが必須です。一方、合同会社・合資会社・合名会社などの持分会社を設立する場合は、定款認証は不要です。
5-3.登記書類を作成
定款が完成したら、次に登記書類を作成し、法務局で法人の設立登記を行います。登記の際に必要となる書類・費用は以下のとおりです。
・法人の印鑑届出書
・出資金の払込証明書
・登録免許税(登録申請1件につき15万円程度)
定款や登記書類は法律的な専門知識を要するため、司法書士に依頼するのが一般的です。作成と申請をあわせて所要期間は9日程度といわれています。費用はかかりますが、手間をかけずに安心して進められる点がメリットです。
5-4.開業届を提出
法人の登記が完了すると、法務局から「登記事項証明書」が発行され、法人として正式に認められます。これをもって、次の各所へ必要な届出を行います。
・年金事務所:厚生年金、健康保険の届出
・公共職業安定所(ハローワーク):雇用保険の届出
・労働基準監督署:労災保険の届出
・各省庁:業種によっては認可申請の手続きが必要
以上が、法人設立に必要なおおまかな流れです。ただし、個々のケースによっては、ここで挙げた以外の手続きが必要となる場合もあるため、不明点があれば、依頼した司法書士に相談するのが確実です。
6.不動産投資の法人化は所得水準によって慎重な判断が必要

不動産投資における法人化は、節税や相続対策といったメリットがある一方で、コストや手間といったデメリットも伴います。したがって、法人化は誰にとっても一律に有利というものではなく、所得水準や将来の投資方針を踏まえて慎重に判断することが求められます。
多くの投資家は、まず個人事業主として不動産投資を始め、収益が一定水準を超えた段階で法人化を検討しています。特に、年間の課税所得が900万円を超えるかどうかが一つの判断基準といえるでしょう。
これから不動産投資を始める方にとっては、最初から法人を設立するのではなく、無理のない規模で始めて経験を積むことが現実的です。その点で、初期費用や管理の手間が比較的抑えられる区分マンション投資は、初心者にも取り組みやすい選択肢といえます。
とくに、単身世帯の増加が見込まれている都市部においては、ワンルームマンションへの投資に安定した需要があるとされています。また、新築ワンルームは供給数が限られているため、競合物件との差別化もしやすい傾向があります。
まずは自分のライフスタイルや資産状況に合った形で不動産投資を始め、将来的に法人化のメリットが見込める段階に達したら、あらためて検討してみるとよいでしょう。

>>【無料eBook】「借金は悪である」という既成概念が変わる本
【オススメ記事】
・副業で考える人生設計|マンション経営も視野に入れた副業の可能性
・首都圏でのマンション経営|覚えておくべき「相場感」を紹介
・始める前に読んでおきたい 初心者向け長期資産運用のコツがわかる本5冊
・土地とマンションの資産価値は?「売却価値」と「収益価値」
・人生はリスクだらけ……でもサラリーマンが行う対策は1つでいい

