

会社員や公務員として働きながら、不動産投資を始めたいと考える人は少なくありません。しかし、副業禁止規定に抵触しないかどうか気になる人も多いでしょう。本記事では、不動産投資が問題になるパターンや行う場合の注意点を解説します。
目次
1.副業禁止でも不動産投資はできるの?

会社員が不動産投資を行う場合、もっとも気になるのは会社の副業禁止規定に抵触するかどうかです。副業といってもさまざまな内容がありますが、不動産投資は基本的に副業とはみなされません。副業禁止の会社であっても、不動産投資は容認されるケースが多いようです。
ただし、事業規模や職業によっては不動産投資が問題になるケースもあるので注意が必要です。次項で不動産投資が副業にあたらない理由と、問題になるパターンを確認します。
2.不動産投資が副業にあたらない理由

不動産投資が基本的に副業に当たらない理由は以下のとおりです。
2-1.相続や譲渡などで不動産を受け継ぐことがあるため
不動産は自分で購入するだけでなく、相続や譲渡などで受け継ぐことがあります。親が遺したマンションやアパートの経営を引き継がなければならないケースもあるため、一概に不動産経営を禁止することは難しいといえます。
また会社の辞令で転勤になったため、一時的に自宅を人に貸し出すケースなどは、元はといえば会社の都合によってやむを得ず行うものです。以上のような理由で不動産投資を禁止できない企業が多いものと思われます。
2-2.本業に支障が出にくいため
会社が副業禁止規定を設ける理由の一つは、本業への影響を防ぐためです。本業終了後に別のアルバイトを行うことで睡眠時間が削られ、翌日のパフォーマンスが低下すれば、会社にとって大きな損失となります。
一方、マンションを1室区分所有する程度の不動産投資であれば、本業に支障をきたす可能性は低いでしょう。不動産管理会社に管理を委託すれば、仕事中に入居者から直接連絡が入る心配もなく、安心して運営を続けることができます。
2-3.情報漏洩が起こる可能性が低いため
会社が副業を認めた場合に危惧するのが情報漏洩の問題です。副業が会社や店舗での勤務なら、他社従業員との会話の中で本業のことを話す機会があるかもしれません。会社としては重要なことを話されては困るという懸念はあるでしょう。
その点、不動産投資は人と接することが少ないので情報漏洩の可能性は低いです。そのため、会社も安心して不動産投資を容認できるという事情があります。
2-4.不動産投資は資産運用としてみなされるため
NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用して資産運用を行うことを政府も奨励しています。不動産投資も基本的に資産運用とみなされます。特に不動産投資は老後資金2,000万円不足問題に備えて資産運用するのに適した商品なので、問題になるケースは稀と考えられます。
2-5.副業は原則自由であるため
そもそも副業を行うことは自由であるという理由もあります。日本国憲法で職業選択の自由が保障されているため、万一会社の副業禁止規定を理由に解雇されても、裁判になれば不当解雇と判断される可能性が高いでしょう。
とはいえ、実際には会社とのトラブルを避けるため、規定に従うのが無難です。不動産投資は副業禁止規定に抵触しないことが多いものの、念のため会社の規定や副業禁止の書面を確認しておくとより安心です。波風を立てずに本業と両立する方法を模索することが大切です。
3.副業禁止の会社で不動産投資が問題になるパターン

副業禁止の会社で不動産投資を行う場合、ケースによっては問題になるパターンもあります。それが事業規模と本業における職業の問題です。
3-1.事業的規模での不動産投資
不動産投資を事業的規模で行うと問題になる可能性があります。事業的規模とは「5棟10室」の基準を超えていることです。一戸建てならおおむね5棟以上、集合住宅ならおおむね10室以上だと事業的規模とみなされます。
これは確定申告の際に事業的規模であるかどうか判断される公的な基準です。アパートで10室の物件ならそれだけで事業的規模とみなされてしまいます。もし新たに不動産投資を始めるなら、区分所有マンションにしたほうが無難でしょう。
3-2.銀行員や公務員は注意が必要
副業を行うのは自由といっても銀行員や公務員の場合は慎重に判断する必要があります。例えば、証券会社の社員が株式取引を禁じられているのは、職務上得た情報を利用したインサイダー取引のリスクがあるためです。同様に、銀行員も会社の規定によっては不動産投資が禁止される場合があります。
一方で、国家公務員が副業を行うには、人事院規則に基づいて事前に申請し、許可を得る必要があります。許可が必要となるのは、以下の条件に該当する場合です。
| 不動産の賃貸 | 以下のいずれかの場合に該当するもの ・一定の規模以上の場合 独立家屋…5棟以上、アパート…10室以上、土地…契約件数10件以上 ・賃貸する不動産が劇場、映画館等の娯楽集会・遊戯等のための設備を備えたものである場合や、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである場合 ・賃貸料収入が年額500万円以上の場合(不動産と駐車場の双方を賃貸している場合は賃料収入を合算する) |
|---|---|
| 駐車場の賃貸 | 以下のいずれかの場合に該当するもの ・駐車台数が10台以上の場合 ・建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場である場合 ・賃貸料収入が年額500万円以上の場合(上記と同) |
| その他 | 上記と同様の事情にあると認められる場合 |
上記の条件に当てはまらない小規模な賃貸を行う場合は申請不要です。一般的に公務員の副業は禁止されているようなイメージがありますが、実際には申請すれば公務に影響を与えない範囲で認められるケースが多いようです。
4.会社員や公務員の副業に不動産投資が適している理由
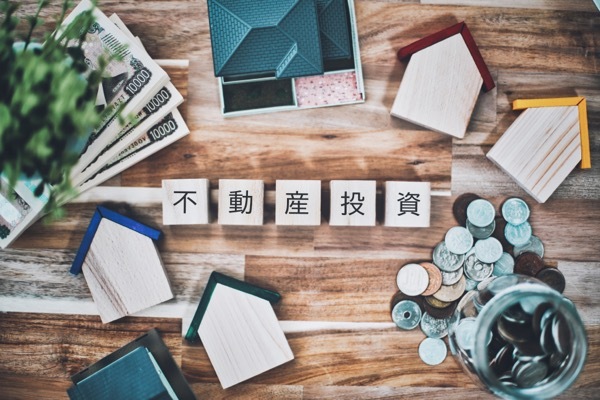
不動産投資は、会社員や公務員の副業に適しているといわれます。それは以下のような理由があるからです。
4-1.時間や手間がかからない
会社員や公務員はフルタイムで働いているため、副業に時間を割くのは難しいのが現実です。しかし、不動産投資の場合は、物件の管理を不動産管理会社に委託することで、手間を大幅に減らすことができます。管理会社に委託すれば、物件の維持管理や入居者募集、家賃回収などをすべて任せることが可能です。
オーナーは基本的に家賃の振込を確認するだけで済むため、時間や労力をほとんどかけずに運営できます。管理委託費は家賃の約5%が相場で、例えば家賃10万円の物件なら5,000円程度となります。コストとしては比較的抑えられており、大きな負担にはなりません。
4-2.金融機関から融資を受けやすい
金融機関は融資審査の際、個人の属性を重視します。特に重要視されるのは、職業、年収、勤務先、勤続年数といったポイントです。会社員や公務員は収入が安定しているため、個人事業主に比べて融資審査に通りやすいというメリットがあります。
公務員は、倒産や業績悪化による失職や給与の減少といったリスクがほとんどないため、信用性が高い職業とされています。また、会社員の場合も、勤務先が上場企業や大企業であれば、個人の属性がより高く評価されます。
さらに、安定した収入があることで、万が一空室が発生した場合でも給与からローンの返済が可能なため、空室リスクにも柔軟に対応できる点が大きな強みです。
4-3.年金や生命保険代わりになる
金融機関と融資契約を結ぶとき、原則として団体信用生命保険(団信)への加入が条件になります。団信に加入すると契約者が万一死亡や高度障害者になった場合に、保険金でローンの残債が支払われます。残された家族はローン残高のない物件を手に入れることができるので、不動産投資が生命保険代わりになるというメリットがあります。
また、団信は「3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)保障」などの特約を付帯することができるので、一般の生命保険並みに保障を充実させることも可能です。
5.副業で不動産投資を始めるときの注意点

副業で不動産投資を始める場合、以下の点に注意する必要があります。
5-1.就業規則を確認し、事前に相談しておく
一般的に、入社時に就業規則について説明を受けることが多いでしょう。もし会社の就業規則で副業が禁止されている場合、不動産投資を始める前に上司に相談し、事前に了解を得ておくのが無難です。
また、就業規則が存在しない、あるいは明確でない場合でも、後から発覚して印象を悪くするのを避けるため、不動産投資や賃貸経営を行う意向を事前に伝え、許可を得ておくと安心です。
5-2.本業に支障が出ない範囲で行う
不動産投資を行う際、本業に支障をきたしてしまっては本末転倒です。会社は、副業による業務への影響を懸念しているため、不動産投資では自主管理を避け、不動産管理会社に委託するのが賢明です。
委託管理を利用すれば、物件の運営をスムーズに進めながら、本業に影響を与えることなく賃貸経営を行うことが可能です。
5-3.事業とみなされない規模で行う
先に述べた「5棟10室以上」の事業的規模を超えないように注意する必要があります。公務員はこの基準に加えて、「年間家賃収入500万円以上」「管理業務を自分で行っている」ことも禁止条項に入るのでよりハードルが高くなります。
会社員でも公務員でも、区分所有マンションを1~2室所有する程度なら問題ありません。相続でアパートを譲り受けたという場合は別として、これから物件を選択するのであれば、区分所有マンションに絞って探すのがよいでしょう。
5-4.本業以外の所得が20万円を超えたら確定申告を行う
本業以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。会社員は給与所得が本業の所得になります。不動産所得は本業以外の所得になるので、ほかの本業以外の所得と合わせて20万円を超える場合は確定申告しなければなりません。
不動産所得とは、家賃収入などから必要経費を差し引いた金額です。万一申告を忘れると、無申告加算税や延滞税などが課税されるので注意が必要です。
5-5.住民税を普通徴収にする
住民税の徴収方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。特別徴収は、給与から天引きされて納税する方法です。一方の普通徴収は、納付書を使って自分で納税する方法で、主に個人事業主などが対象になります。会社員は給与から天引きしてくれるので納税の手間はありませんが、不動産投資を行っている場合は支障が出ます。
不動産投資を行っている会社員が不動産所得を含めて確定申告をした場合、住民税を特別徴収のままにしておくと、不動産所得による税額も一緒に天引きされてしまいます。会社の経理に不動産による利益がどれくらいあったかを知られてしまうので、普通徴収を選択したほうがよいでしょう。確定申告書を記入する際に「自分で納付」を選べば普通徴収になり、会社には税務署から通知が行きません。
6.副業で不動産投資を始めるときの6ステップ

副業で不動産投資を始めるには、以下の6つのステップを踏むのが一般的です。
6-1.不動産投資に関する知識を深め、情報を集める
まずは、不動産投資に関する知識を深め、情報を集めることから始めます。初期費用がどれくらいかかるか、表面利回りと実質利回りの違い、法定耐用年数と減価償却の関係、確定申告のやり方、新築と中古のメリット・デメリットの比較、不動産会社の選び方など、把握しておきたい項目はたくさんあります。
知識や情報を得る方法としては、インターネットや書籍で学ぶだけでなく、不動産会社が開催するセミナーに参加するのも有効です。
6-2.投資の目的やゴールを明確に設定する
不動産投資は、目的やゴールを明確にしてから始めることが大事です。ライフスタイルに合わせて目標とゴールを設定します。例えば、老後資金を用意するために不動産投資を始める場合、目的は老後生活に年金以外の収入を得ること。そして、ゴールは公的年金が支給開始となる65歳となります。
ローンを完済すると、家賃収入から毎月の諸経費を差し引いた金額を生活費として使えるようになります。したがって、35年ローンを65歳で完済するには30歳で不動産投資を始める必要があります。
6-3.物件を選定し、収支シミュレーションを行う
目的やゴールを明確にしたら、次は具体的な物件の選定に進みます。まずはモデルとなる物件を選び、収支シミュレーションを行ってキャッシュフローがプラスになるかを確認しましょう。試算結果に納得できれば、不動産会社を訪れて相談します。不動産会社との話し合いで希望条件に合う物件を提案してもらい、納得できれば購入を決定します。
物件選びは、不動産ポータルサイトを活用するのが一般的ですが、不動産会社との面談で目的やゴールをしっかり伝え、条件に合った物件を紹介してもらうのも有効な方法です。
6-4.不動産投資ローンの申し込みと審査を進める
購入したい物件が決まったら金融機関に不動産投資ローンの申し込みを行います。返済方法は毎月の返済額に大きな影響を与えるので、慎重に判断します。選択する項目は「返済期間」「元利均等返済または元金均等返済」「固定金利または変動金利」などです。
返済方法を決定したら申し込み手続きを行い、融資審査を受けます。
6-5.物件の購入手続きを完了する
融資審査に通ったら物件の購入手続きを完了します。物件を購入する際には以下のような諸費用がかかります。
・ローン事務手数料
・ローン保証料
・火災保険と地震保険のセット保険料
・登録免許税
・司法書士報酬(登記手続きを依頼した場合のみ)
・不動産取得税
・印紙税
・固定資産税などの清算金(前オーナーとの清算のため、新築の場合は不要)
6-6.賃貸物件として運用をスタートする
物件の引き渡しを受けた後、登記手続きを完了させ、不動産管理会社に管理を委託します。管理会社が入居者募集や物件管理を代行し、入居者が決まり次第、賃貸経営が本格的にスタートします。
7.ダブルワーク時代における不動産投資の可能性
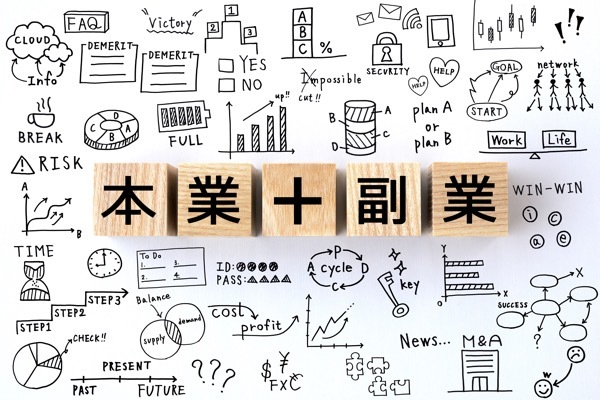
不動産投資が副業に該当しないことを確認しましたが、近年の労働環境もその追い風となっています。
実質賃金の低下により、1つの仕事だけでは十分な収入を得られず、ダブルワークを選ぶ人が増えています。また、「103万円の壁」による働き控えや人手不足の影響も深刻化し、企業側も副業を禁止し続けることが難しい状況にあります。こうした背景から、副業を禁止する風潮は徐々に時代遅れとなりつつあります。
ただし、会社員や公務員の場合、本業に支障をきたさないことが大前提です。そのため、大規模な投資は避け、賃貸需要が高い東京・横浜・名古屋などの大都市圏で、駅徒歩10分以内の新築ワンルームマンションといった小規模な物件から始めるのがおすすめです。区分所有マンションは公務員でも副業規定に抵触しにくく、安心して運用できます。
これから不動産投資を検討している方は、副業規定を過度に心配せず、まずは不動産会社に相談してみるとよいでしょう。
>>【無料eBook】「借金は悪である」という既成概念が変わる本
【オススメ記事】
・副業で考える人生設計|マンション経営も視野に入れた副業の可能性
・首都圏でのマンション経営|覚えておくべき「相場感」を紹介
・始める前に読んでおきたい 初心者向け長期資産運用のコツがわかる本5冊
・土地とマンションの資産価値は?「売却価値」と「収益価値」
・人生はリスクだらけ……でもサラリーマンが行う対策は1つでいい

