
マンションの購入に際して、新築か中古かという選択は多くの人が悩むポイントのひとつです。インターネットでは「新築マンションは買うな」といった内容もあり、漠然とした不安を感じている方もいるかもしれません。
住宅は人生で最も大きな買い物のひとつです。高額なローンを組み、長く住む場所を選ぶという決断に、迷いが生じるのは当然のこと。誰だって「買った後に後悔するのは避けたい」と思うものです。
この記事では、「なぜ『買うな』と言われるのか?」という疑問を出発点に、新築マンションのデメリットだけでなく、メリットや他の選択肢と比較したときの視点も含めて、後悔しない判断をするためのヒントをお届けします。
目次
「新築マンションは買うな」とされる5つの理由
新築マンションは、最新の設備や美しい外観、販売会社の手厚いサポートなど、一見すると魅力が詰まった商品に見えます。しかし、実際には「買うべきではない」とする声も根強く存在します。その背景には、購入後に想定外の事態や後悔を招く可能性がある構造的なリスクがあります。ここでは「新築マンションを買うな」と言われる理由を紹介します。
新築プレミアムの剥落による価値の低減
新築マンションは最新の設備や住環境の整った住まいとして高い人気を誇りますが、その販売価格には「新築プレミアム」と呼ばれる付加価値が含まれていることが一般的です。これは新しいものに対する市場の期待値を反映したもので、購入直後にはそのプレミアム分が少しずつ市場価格に調整されていく傾向があります。
たとえば、引き渡し後に居住を開始した新築物件は、築年数が浅くても中古物件として扱われます。そのため、周辺の中古市場と比較されやすくなり、結果として販売価格よりも下回る価格で評価されるケースも見受けられます。
もちろん、立地やブランド力によっては資産価値を維持しやすい物件もありますが、「買ってすぐ売る」ような短期的な視点だと価格調整の影響を受けやすい点は、事前に理解しておくべきポイントです。
広告やモデルルームと実際の暮らしのギャップ
モデルルームや広告に使われる画像・演出は、理想的な暮らしをイメージさせるために非常に洗練されています。しかし、実際の住戸では眺望、日当たり、騒音、隣接住戸の生活音など、日常的な要素にギャップを感じることも少なくありません。
さらに、モデルルームに使われている内装オプションが標準仕様ではないケースも多く、実物との差異に後から気づいてがっかりする声もあります。
修繕積立金や管理費が将来上がる可能性がある
新築マンションの販売初期には、住民の負担感を抑えるために、管理費や修繕積立金が比較的低く設定されるケースがあります。しかし、これは将来的な引き上げを前提とした初期設定である場合があり、築10年・20年と経過する中で徐々に増額される事例もあります。
販売優先で立地や将来性が犠牲になっている場合がある
大規模な新築分譲マンションの中には、土地の取得コストを抑えるため、利便性や将来性に乏しい立地に建てられるケースもあります。 目先の間取りや外観だけで判断すると、駅から遠い・買い物が不便・再開発の見込みがないといった“立地リスク”を見落としてしまうことがあります。
住民の質や管理体制が未確定
新築マンションでは、入居が始まるまで住民の層やコミュニティの雰囲気、管理組合の運営方針がわかりません。中古マンションであれば、過去の管理状況や住民構成の実態がある程度把握できますが、新築は“未知の箱”でもあります。
住環境の質は、物件スペックだけでなく「誰とどう住むか」にも影響されます。この点も、新築特有のリスクといえるでしょう。
関連記事:新築マンション投資とは?中古と比較した時のメリットや注意点、失敗事例を紹介
新築マンションを購入するメリットとは?
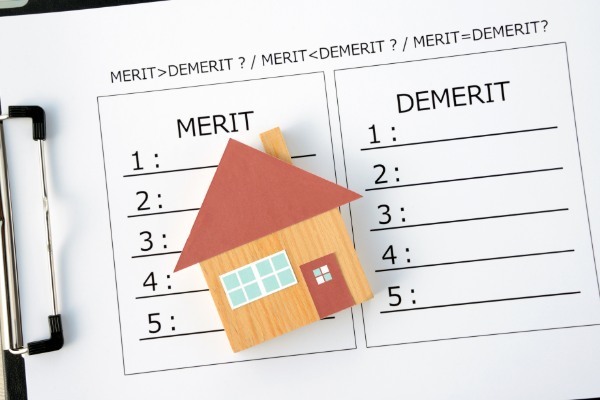
「新築マンションは買うな」という意見がある一方で、新築マンションには確かな魅力もあり、それを正しく理解したうえで選ぶことが、納得のいく住まい選びにつながります。新築マンションだからこそ得られる主なメリットを確認していきましょう。
最新設備が標準で整っている
新築マンションは、建築当時の最新の住環境技術や設備仕様が取り入れられているのが大きな特徴です。たとえば以下のような点が挙げられます。
- 高断熱、高気密な窓や壁材
- 玄関のスマートロックやセンサー付き照明などのIoT設備
- キッチン、浴室などの最新水回り設備
住宅ローン控除などの税制メリットが受けられる
新築マンションを購入する場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用条件や控除額が、中古物件に比べて優遇されるケースが多く見られます。特に近年の制度では、控除期間が13年間(従来は10年間)に延長される措置が取られており、一定の要件を満たす新築住宅であれば、この恩恵を受けることができます。
たとえば、借入額が4,000万円の場合、住宅ローン控除によって毎年約28万円の税額控除が受けられ、13年間の合計では最大で約364万円もの節税効果が期待できます。 これは、初期費用や将来のリフォーム資金などに充てることも可能な、大きなメリットと言えるでしょう。
※実際の控除額は、年々のローン残高の減少や所得税・住民税の納税額によって変動します。制度内容も変更される場合があるため、最新の情報と個別条件を確認したうえでご検討ください。
さらに、購入時の税負担を抑えるための優遇措置も用意されています。具体的には、
- 登録免許税の軽減(所有権保存登記、抵当権設定登記において税率が引き下げられる)
- 不動産取得税の軽減(新築住宅については課税標準額の特別控除が適用される)
などがあり、物件価格に応じて初期費用を大幅に圧縮できる可能性があります。
ただし、これらの控除や軽減措置は、住宅の床面積要件や所得制限、適用期限(購入・入居時期)など、細かな条件が設けられています。制度は年度ごとに改正されることもあるため、購入検討時には最新情報を確認することが重要です。
アフターサービスや長期保証制度が充実している
新築マンションを購入する大きなメリットの一つが、充実したアフターサービスと長期保証制度です。多くの新築物件では、引き渡し後も安心して生活できるよう、一定期間内に発生した不具合や故障に対して、無償または低額で修理・対応する仕組みが整えられています。
特に重要なのが、構造躯体と呼ばれる建物の基幹部分に対する10年間の瑕疵担保責任です。これは、住宅の品質確保の推進等に関する法律(品確法)により義務付けられているもので、たとえば基礎・柱・梁など、建物の安全性に関わる重大な部分に不具合が生じた場合、無償で修補を受けることができます。
参考:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(国土交通省)
また、これに加えて、多くのデベロッパーでは独自に設備保証や内装に関する短期保証も設けています。たとえば、キッチンや浴室などの水回り設備に対する2年間保証、内装仕上げ材(クロスの剥がれ、床鳴りなど)への1〜2年間保証 といった形で、生活に直結する細かな部分もカバーされているのが一般的です。
加えて、定期点検の実施(1年目、2年目など)を標準サービスとして行っている物件も多く、住み始めてから気づきにくい初期不具合を早期に発見・対応できる仕組みも整っています。
このようなアフターケア体制が整っていることで、万が一のトラブル時にも専門のサポートを受けることができ、住み始めたばかりの時期に感じがちな不安を大幅に軽減できる点は、新築ならではの安心材料といえるでしょう。
第一入居者として自由に住まいをカスタマイズできる
入居時にリフォームや原状回復を気にせず、自分のスタイルに合わせて空間を整えられる点も新築のメリットの一つです。家具の配置や収納の工夫など、暮らしの自由度を重視する方にはぴったりの選択肢といえるでしょう。
“買っていい新築”と“やめておくべき新築”を見分けるポイント

新築マンションの購入を検討する際に、「買うべきか・買わないべきか」だけでなく、「どんな新築マンションなら買っても後悔しにくいか」という視点を持つことが非常に重要です。ここでは、物件選びの際に注目すべきポイントを整理していきます。
立地
マンションの資産価値に最も大きく影響するのが立地です。購入時だけでなく、将来の売却を見据えた際に、立地条件は物件の「価値」を左右する重要な判断基準になります。
まず、現在の生活利便性は必ず確認しておきましょう。具体的には、最寄駅までの徒歩距離(徒歩10分以内は高評価)、スーパーやドラッグストア、医療機関、教育施設などが徒歩圏内にあるかがポイントです。日常生活のしやすさは、居住満足度を大きく左右するため、見落とせない観点です。
加えて、将来的な発展性や街の成長ポテンシャルも考慮する必要があります。たとえば、周辺エリアで大規模な再開発が計画されているか、公共交通機関の整備やバイパス建設が予定されているかといった、インフラ拡充計画の有無は、将来の資産価値維持に大きな影響を与える可能性があります。
さらに、人口動態にも目を向けることが重要です。地域の人口が減少傾向にある場合、将来的に需要が細り、物件価値が下落しやすくなるリスクがあります。一方で、子育て世代の流入が続いているエリアや、高齢者向けインフラが整備されているエリアなどは、安定したニーズが期待できるでしょう。
このように、現在の利便性と将来の成長性をバランスよくチェックすることが、長期的な満足度と資産性の両立につながります。目先の価格や設備だけでなく、街全体の未来にも目を向けて検討することが、後悔しない新築マンション選びのポイントです。
管理体制
管理体制の良し悪しは、住み心地だけでなく、将来的な資産価値にも大きな影響を与えます。特に新築マンションの場合は、まだ管理組合が本格的に機能していないケースも多いため、事前に「管理に関する方針や準備状況」をしっかり確認しておくことが重要です。
まず、長期修繕計画がきちんと策定されているかを確認しましょう。 長期修繕計画とは、建物や共用部分の劣化に備え、10年後、20年後、30年後にどのような修繕工事を行い、どれくらいの費用がかかるのかを見積もった計画書です。これが不十分だと、将来、突然の高額な修繕費負担が発生したり、建物の劣化によって資産価値が大幅に下落したりするリスクがあります。
また、管理会社の実績や評判も大きな判断材料となります。管理会社がどれだけ適切に清掃・点検・修繕計画の運営を行っているかは、住み始めてからの快適性に直結します。近年では、管理品質に差がつきやすくなっており、管理の行き届いた物件は資産価値を維持しやすい傾向にある一方、管理がずさんなマンションは築年数以上に資産価値が下落するケースもあります。
共用部(エントランス、廊下、ゴミ置き場、駐輪場など)の管理・清掃レベルも、物件の「第一印象」や日常の快適さを左右します。モデルルームや完成建物見学会では、建物内部や共用部の清掃状態、設備のメンテナンス状況にもぜひ目を向けてみましょう。
これらの情報は、販売時に渡されるパンフレットや重要事項説明書に記載されていることが多く、購入前に確認することが可能です。また、モデルルームでは直接担当者に質問し、「管理組合の立ち上げ時期」「修繕積立金の増額予定」「管理会社との契約条件」などを具体的にヒアリングしておくのも有効です。
販売会社や施工会社の信頼性
マンションは長期間にわたって住み続ける資産である以上、「どこが建てたか」「誰が売っているか」という点は、見た目以上に重要な判断材料です。施工会社や販売会社の信頼性は、住まいの品質や購入後の満足度に直結します。
たとえば、過去にどのような物件を手がけてきたか、その中でトラブルや不具合の事例があるかどうかは、購入前に一度確認しておきたいポイントです。また、アフターサービスの内容や対応の柔軟さも、万が一の不具合時に安心できるかどうかを左右します。
さらに、財務基盤が安定している会社であれば、将来的なサポートの継続性という点でも安心材料となります。企業の規模だけで判断せず、情報開示や実績を丁寧に調べることが、後悔のない選択につながるでしょう。
物件の資産性
自宅として新築マンションを購入する場合でも、将来的に転勤や住み替え、相続といった可能性がある以上、「もし売る・貸すことになったらどうか」という視点も持っておくことが大切です。いわゆる“資産性のある物件”とは、長期にわたり市場で価値が評価されやすい特徴を備えています。
たとえば、購入時の価格が周辺相場と比べて適正かどうか、間取りや専有面積が流通市場で支持されやすい汎用性の高いものであるか、そして物件自体やエリアに独自の魅力やブランド力があるかどうかといった点が挙げられます。
こうした観点から冷静に検討することで、単に「住む場所」ではなく、「将来の資産」として納得できる選択が可能になります。
「買うな」といった意見だけに流されず、自分の軸で判断しよう
「新築マンションは買うな」といった意見には、確かに一定の根拠があります。新築プレミアムによる価格調整、将来の修繕費負担、生活環境の見えづらさなど、見落としがちなリスクが存在するのも事実です。
しかし一方で、新築ならではの安心感や快適性、税制面のメリット、そして第一入居者としての自由度といった価値も、間違いなく魅力として存在します。
大切なのは、誰かの意見やネット上の声に振り回されるのではなく、「自分と家族にとって何が本当に必要なのか」「どんな暮らし方を大切にしたいのか」という軸を持って判断することです。
物件選びは、価格だけでなく、立地、設備、管理、周辺環境、そして将来的な資産価値など、複合的な視点からの総合判断が求められます。迷ったときこそ、一度立ち止まって「なぜその選択をしようとしているのか?」を問い直してみてはいかがでしょうか。
【オススメ記事】
・副業で考える人生設計|マンション経営も視野に入れた副業の可能性
・首都圏でのマンション経営|覚えておくべき「相場感」を紹介
・始める前に読んでおきたい 初心者向け長期資産運用のコツがわかる本5冊
・土地とマンションの資産価値は?「売却価値」と「収益価値」
・人生はリスクだらけ……でもサラリーマンが行う対策は1つでいい

