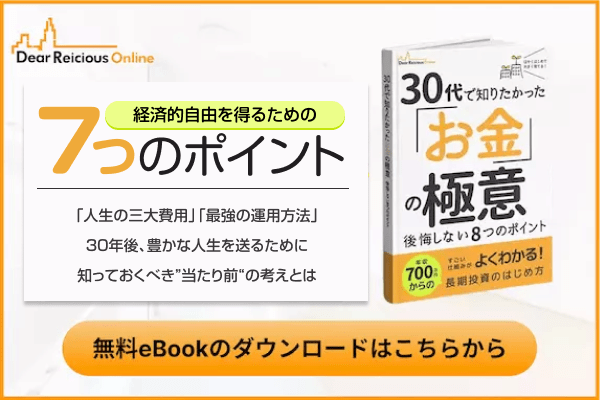マンション経営を行うと多くのメリットを享受できる反面、リスクもいくつか存在します。天災をはじめとするほとんどのリスクは保険などを用いることでカバーすることができますが、マンション経営において空室リスクを回避する手段はなかなか思い当たらないかもしれません。しかし、最初の物件の購入後、ある程度資産に余裕ができた場合には、追加で借入を行い、1室、2室と部屋数を増やすことで空室リスクを軽減させることが可能となります。一方で、一定の不動産規模を超えると、個人であっても、個人事業主として不動産事業を行っているとみなされるようになります。そこで今回は、不動産所得を事業的規模にすることで得られる税金面でのメリットについて考えてみたいと思います。

複数物件はリスクを低下させる
マンション経営は長期的で堅実な運用が基本ですから、無理に複数物件を保持する必要はありません。複数物件の保持は、返済に見合う収入があることが前提です。しかし家賃収入とローンの返済のバランスが取れているのであれば、複数物件を持つことはリスクの低減につながります。
1室だけで行うマンション経営では、空室、事故、周辺の環境変化などが起きたときに、機能不全を陥る可能性がありますが、物件数が2室、3室と増えると、1室で収益が見込めなくなったとしても、他の物件からの収益で補うことができます。結果的にマンション経営のリスクは小さくなるのです。
投資知識のない人からすると、物件の購入は数が増えるほどリスクが大きくなるように見えるかもしれません。しかし、物件を複数所有することは、収益性の向上だけでなくリスク分散も同時に行える、理にかなった行動といえるのです。
規模の拡大による事業的規模の認定と問題点
マンション経営では、規模拡大で収益性が高まり、リスク低減効果が期待できますが、「5棟10室基準」という水準に達すると、不動産賃貸業を営む事業者としての認定が受けられるようになります。この5棟10室基準とは、例えば、一戸建てであれば5戸。ワンルームマンションのような区分所有物件であれば10室。その他に駐車場などは5台駐車分で1室とカウントされます。
事業的規模とすることにはメリットもありますが、デメリットもあります。よく知られているのは、副業を禁止した就業規則に違反する恐れが出てくることでしょう。特に公務員の方は要注意です。5棟10室基準に達してしまったために、マンション経営規模の縮小か、懲戒免職かという事態にまで陥ったケースもあります。現在の勤務先の就業規則次第で、5棟10室基準の適用を避ける必要が出てきます。
事業的規模で変化する税金と経費
5棟10室基準を満たし、事業的規模とするか否かで、マンション経営に関わる収益性と税金は大きく変わります。所得税の区分である不動産所得と事業所得と山林所得には、複式簿記で損益を記録することにより、青色申告特別控除の適用が受けられます。事業的規模ではない不動産所得の控除額は10万円ですが、事業的規模として青色申告をすると、控除額は65万円まで跳ね上がります。差額55万円分の所得控除は、大きな節税効果をもたらしてくれるといえるでしょう。
また、事業的規模となると、「青色事業専従者」という制度の利用が可能になります。これは配偶者や一定の条件を満たした親族が事業を手伝った場合、支払った給料を経費として計上できる制度です。基礎控除などの所得控除の関係で、1人で1,000万円稼ぐよりも、2人で500万円稼いだほうが、税金は安くなりますので、専従者を利用して、収益を分散させ、さらなる節税効果を得ている人もいます。
しかし、事業的規模とすることで、新たに個人事業税という税金が発生します。これは利益が290万円以上の場合、それを超えた金額に5%の税金を課すというものです。また、所得税も、個人や個人事業主の場合、高額所得者ほど税率が高くなる累進課税が採用されています。不動産所得の規模を大きくする場合は、こうしたデメリットも考慮したうえで、それに対する対応策を検討しておく必要があります。
複数物件によるリスク分散も検討に
今回は、投資不動産を多く持って「事業的規模」とすることで、どのようなメリットやデメリットが生じるかを明らかにしてきました。マンション経営は規模が大きいほどスケールメリットが働きます。一室だけですと、空室リスクなどの影響を受けやすいのですが、物件数を増やすことでリスク分散が可能になります。
また、税金面では、「5棟10室基準」に達するかどうかがひとつの鍵になります。事業的規模の認定を受ければ、青色申告特別控除や青色事業専従者の利用など節税効果が期待できますが、一方でデメリットもあります。どちらを選択するべきか、ご自身の財務状況などから、相対的に判断する必要があるでしょう。
>>【無料eBook】「借金は悪である」という既成概念が変わる本
【オススメ記事】